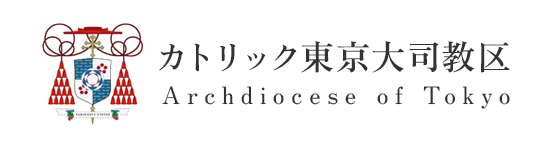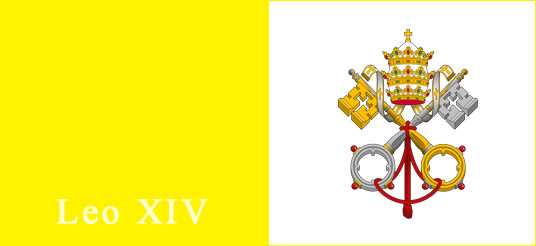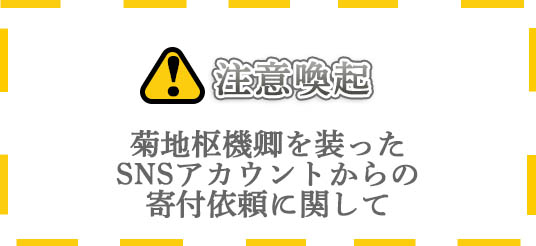教区の歴史

年間第17主日説教
2016年07月24日
2016年7月24日、小岩教会
説教
主イエスは弟子たちの求めに応じて、「祈り」をお教えになりました。イエスが教えてくださった祈りが、わたしたちのよく知っている、日々唱えております「主の祈り」であります。
そして、更にイエスは続けて言われました。
「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく者には開かれる。」(ルカ11・10)
大変有名な教えであります。前後の文脈から言って明らかに、この教えは
神に祈り求めなさい
と言うことを教えていると思います。
神に祈り求めるならば、その祈りは必ず聞き遂げられる、と教えています。
しかし、時として、祈りが聞き入れられなかったという思う体験をもっていないでしょうか。
このことに関して、ヨハネの福音が同じ趣旨を教えています。
「わたしの名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、わたしがあなたがたを任命した。」(ヨハネ15・16) 「あなたがたがわたしの名によって何かを願うならば、父はお与えになる。今までは、あなたがたはわたしの名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなたがたは喜びで満たされる。」(ヨハネ16・23-24)
イエスの名によって願うならば、イエスはわたしたちの願いを天の父に取り次いでくださいます。わたしたちは、いつも主イエス・キリストによって、と言って祈りを献げています。
わたしたちの祈りは、イエスが取り次いでくださるのにふさわしい願いでなければなりません。とても、そういう祈りはお取り次ぎできないというような内容であってはならないでしょう。
併せて、新約聖書の中にある、ヤコブの手紙の教えを思い出します。
「あなたがたは、欲しても得られず、人を殺します。また、熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。得られないのは、願い求めないからで、願い求めても、与えられないのは、自分の楽しみのために使おうと、間違った動機で願い求めるからです。」(ヤコブ4・2-3)
願い求める時の動機が大切と言っています。
わたしたちは、どのような動機で願い求めているでしょうか。
自分の欲望の満足のための祈りを、神様はお聞き入れにはならない。
さて、今日の福音は「主の祈り」を教えております。主の祈りは、前半と後半に分けて考えることができます。そして、結びの祈りを思い出しましょう。
「わたしたちを誘惑におちいらせず、悪からお救いください」。
この悪という言葉ですが、悪魔と訳すことも可能であります。悪いものと訳す場合もあるそうです。
わたしたちはミサの交わりの儀、御聖体拝領の前に、必ず主の祈りを献げ、さらにその後、司祭は副文で次のように祈っています。
いつくしみ深い父よ、すべての悪からわたしたちを救い、
現代に平和をお与えください。
あなたのあわれみに支えられすべての罪から解放されて
すべての困難にうち勝つことができますように。
わたしたちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを
待ち望んでいます。
わたしたちの願い求めるべき事柄は、結局「主の祈り」の後半の祈りに尽きるのではないでしょうか。そして、わたしにとりましてはさらに「すべての悪からお救いください。すべての悪からお守りください。」という祈りにまとめられると思います。
みなさんは、いつどのような動機で信者になられたでしょうか。わたしは大学生の時に洗礼を受け、カトリック信者になりました。
ずっと、わたしの心にあった疑問は、神がいるのに、どうしてこの世には悪いことが起こるのでしょうか、という疑問であります。
「わたしたちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。」と司祭は唱えます。
この世界、そしてわたしたち人類は、さまざまな出来事の中で、神の救いのみわざが完成する日を待ち望んでいるのであります。まだ途中なのです。もっとも、人間は時間の中で生きていますが、神様の世界は時間のない世界ではないかと思います。
この世界の中で、わたしたちひとり一人、自由な判断と決断をすることができるものとして造られています。
日々わたしたちは神様の声に耳を傾け、神様との対話の中で、神様のみむねを行う力を願い求めています。そして、今日の第二朗読で使徒パウロが言っておりますように、神様は、御子イエス・キリストを十字架におつけになることをお許しになり、わたしたちの罪をすでにお赦しになってくださっている、わたしたちは罪を赦され、そして、わたしたち自身、神の前にかけがえのない大切な存在とされている、という信仰を今日も深く心に刻みたいと思います。