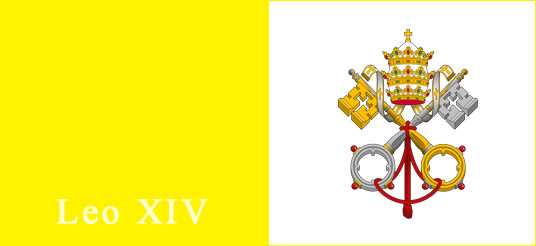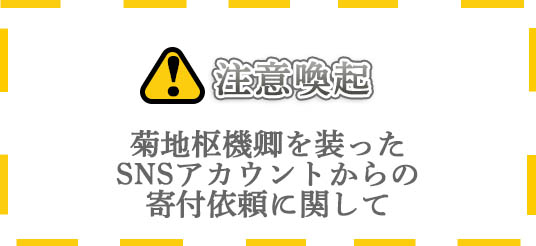教区の歴史

エルサレムのチリロ青山謙徳(1922.3.18~2012.11.19 90歳)葬儀ミサ説教
2012年11月22日
2012年11月22日 東京カテドラル関口教会にて
青山謙徳神父は19日月曜日の午後、90年の生涯を終え、60年の司祭生活をまっとうして、天の神様のもとに帰って行かれました。
10年前、司祭叙階50年を記念して『綴りかた』という本をお作りになりました。そこに謙徳神父のお母様の最期の話が載っています。
今から40年前、謙徳神父が50歳の時に、お母様は直腸がんで亡くなられました。当時は今ほど痛みのコントロールの技術が進んでいない時代でしたから、がんの末期はたいへんな痛みと戦わなければなりませんでした。お母様はそのことを考えて、謙徳神父に、聖歌のテープを用意して、枕元で流してほしいと頼んだそうです。自分は痛みの中で祈ることもできなくなるかもしれない。でも聖歌を聞いていたら最後までせめて神に心を向けていることはできると思う。謙徳神父はお母様の臨終の枕元で、実際に聖歌のテープを流してさしあげたそうです。
今週月曜日の朝、病院からの知らせでわたしたちペトロの家のスタッフは病室に駆け付けました。謙徳神父はそれほど苦しまれている様子ではありませんでしたが、もうほとんど反応がありませんでした。わたしたちは謙徳神父の枕元で聖歌を歌いました。ご家族も駆けつけて、甥御さんがラテン語のミサの録音も流しました。聞いて分かっていらしたようです。今になってみるとお母様と同じように最期まで神様に心を向けて逝かれたのだと思います。
まだ話ができたとき、わたしに向かっておっしゃった最後の言葉は「最後まで神さまに忠実でいられるように、願っています」という言葉でした。本当に最後の最後まで信者として、司祭として忠実に歩まれたと思います。ですから、記念のカードに印刷する聖句をどこにするか相談されたとき、マタイ25章、タラントンのたとえ話の中の言葉が浮かんできました。
「忠実な良い僕だ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。」(マタイ25・21)
青山謙徳神父は祖父の代からのカトリック信者でした。おじいさまは新潟でパリ外国宣教会のツルペン神父から洗礼を受けました。ツルペン神父はそのおじいさまに教会で働くよう勧めましたが、商売の関係ですぐには従えなかったそうです。商売がうまく行かなくなって、晩年は東京に出てきて教会の仕事をするようになりました。二代目の青山少年は、小さいころから司祭になりたいという望みを持っていましたが、貧しくて、かないませんでした。フロジャク神父の勧めで、結婚して伝道士になりました。それからずっとこの関口教会に住み込んで、伝道士として働きました。
謙徳神父は長男でした。この関口教会で生まれ、育ちました。自分の希望で小神学校に入りました。ご両親は息子が神父になることを望んでいましたが、謙徳神父が司祭に叙階されるまで一度もそのこと言わずに、見守っていてくれたそうです。実に三代かけて実った召命でした。そして弟の和美神父も後に続きましたし、一人の妹さんはシスターになりました。
青山謙徳神父のことは、戦争体験を抜きにしては語ることができないと思います。神学生の時に召集され、陸軍の将校になって23歳の時、中国で終戦を迎えました。その体験はその後の長い人生に大きな影響を与えました。
軍隊の中で、兵隊同士の強固な連帯感、友情を体験し、戦後もずっとそのつながりを大切にしていました。日本が中国人の地を蹂躙し、そこでさまざまな身勝手な行動をしたことを申し訳ないと反省しておられました。終戦後の日本人に対する中国人の寛大な態度には深い感銘を受けたそうです。肉体的にも戦争体験をずっと引きずっておられました。戦時中に受けた乱暴な手術の後遺症に生涯悩まされたのです。それは本当に当事者としての戦争体験でした。ですから当事者ではない後の世代の人々が日本の戦争責任とか、さらに教会の戦争責任と言って、当時の立場があった人々を責めるかのような発言をすることにたいへん心を痛めておられました。と同時に「日本は確かに悪いことをした」とおっしゃった言葉もわたしの心に残りました。そして戦争を二度と繰り返してはならないという思いを抱きながら、戦争で亡くなった人々のために祈り続けておられました。
中国で敗戦後の処理をしていたため、日本に帰ったのは1946年のことでした。そのころの話をペトロの家の食卓で話してくださったことがあり、わたしの心に残っています。
東京に帰ってきて、すぐに神学校に戻ろうとしたのですが、許可が出なかったそうです。召集されて、兵隊に行っただけならいいが、将校になったということは自ら進んで戦争に加担したことであり、そういう人間は司祭にふさわしくないというのがその理由でした。好んで将校への道を選んだわけではなかったのですが、事情を理解して復学が認められるのは簡単でなかった、そんな話をしてくださいました。
もう一つの話は復学後のことです。当時の神学院の院長が、ある日、軍隊帰りの神学生たちに向かって「残念だが君たちは司祭になれない。戦争で人を殺しているから、それが叙階の障害になる」と言ったそうです。確かに敵に向かって銃を撃っていたので、誰かを殺したかもしれない。もうこれで司祭への道は絶たれたと思ったそうです。しかし、第二次大戦後のことですから、全世界にそういう神学生が大勢いました。そこでバチカンから叙階障害の特別な免除が与えられ、やっと司祭になることができたというのです。
ですから謙徳神父さんにとって、司祭職とは本当に神の恵みでした。
その後、小岩、八王子、洗足などの教会や幼稚園でほんとうに忠実に司祭職、園長職をまっとうされたことについては、ここにお集まりの皆様がよくご存じだと思います。
この葬儀ミサの福音で、タラントンのたとえ話を呼んでいただきました。ただし、1タラントンの人の結末は省かせていただきました。5タラントン、2タラントン預かった人と謙徳神父を重ね合わせて思い起こしていたからです。謙徳神父は、自分のいのちを、自分の司祭職を神からあずかった「タラントン」のように受け取っていたと思います。自分の力で獲得したものではない。あたりまえに自分が持っているものでもない。特別な神からの恵みとして神様からあずかっているもの、だから最期の最期、神様にお返しするまで忠実に生きたい、それが謙徳神父の願いでした。今、神様のもとへ行き、「忠実な良い僕だ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ(主人の喜びに入りなさい)」という神様の言葉をいただいているに違いありません。
「忠実」は、ギリシア語でpistosと言います。この言葉は形容詞で、「pistis=信仰」という名詞とつながっています。「信頼に値する=忠実な」という意味と「信頼している、信仰を持っている」という両方の意味があります。青山謙徳神父の「忠実さ」はこの神への「信仰・信頼」に基づく生き方でした。その信仰とはすべては神様の計らいであり、神に信頼し、すべてを神にゆだねるのが一番良い、という信仰でした。
神と教会に対する忠実さを貫いた青山謙徳神父を忍びながら、その生涯にわたる神の導きに感謝し、謙徳神父をいつくしみ深い神のみ手におゆだねしましょう。そして、残されたわたしたちが、謙徳神父の姿を思い起こしながら、神に対する忠実と信仰の道を歩んでいくことができるように、心を合わせて祈りましょう。