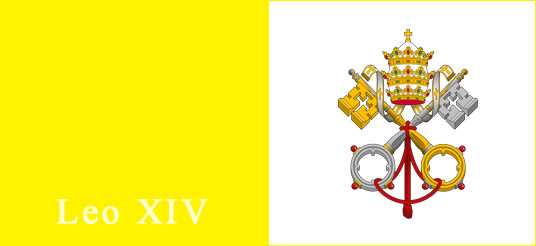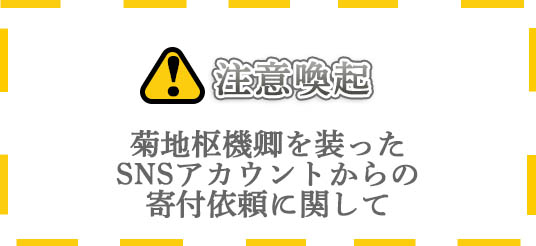教区の歴史

「司祭が司祭であることの意味」
2010年07月01日
・・・『神学ダイジェスト』2010年夏 108号 特集 「司祭養成によせて」巻頭言
昨年の6月19日(イエスのみ心の祭日)から今年の6月11日(イエスのみ心の祭日)までの「司祭年」が終わろうとしている。司祭年とは、世界のある地域での極端な司祭召命の減少と司祭のスキャンダル多発という現実の中で、「司祭が司祭であることの意味」をもう一度見つめ直すためのものであったと思う。この一年の中でわたしにとって特に印象深かったのは、昨年秋の「日韓司教交流会」で聞いた話だった。
キム・スーハン枢機卿の司祭職への決断
昨年11月、大阪教区を会場にして開催された日韓司教交流会の一つのテーマは、「キム・スーハン(金寿煥)枢機卿の生き方を学ぶ」であった。2009年2月16日、86歳で亡くなられたキム・スーハン枢機卿について、ここで詳しく紹介する必要はないだろう。1970年代~80年代の韓国の独裁政権の時代に、キム枢機卿はソウル大司教であり、民主化運動の活動家たちを身を挺して守ったこと、それをとおして、韓国社会の中で「カトリック教会は人間を守る」という大きな信頼が得られるようになったことはあまりにも有名である。カン・ウィル(姜禹一)チェジュ教区司教が、キム枢機卿について語ってくれた(カン司教はもともとソウル教区司祭で、ソウル教区の補佐司教として長い間、キム枢機卿のもとで働いた)。
「キム・スーハンの家は貧しく、病気の母親の薬を買う金がなかった。少年キム・スーハンの夢は、大人になったら商人になって金を儲け、母親のために薬を買う、というものだった。しかし、その母親から『お前は神父になりなさい』と言われて小神学校に入った。キム神学生は司祭になりたいという思いがはっきりしないまま、神学校での生活を続けた。彼が助祭になったとき、朝鮮戦争が起こった。キム神学生はソウルの神学校にいたが、他の人々ともに一緒にプサンまで逃げた。戦争の最初のころ、北の軍隊は圧倒的な力で南下してきて、南の人々はプサンに追い詰められた。完全に北側の勝利に終わるかもしれなかった。そのプサンでキム・スーハンが聞いたのは、北の軍隊の侵攻により、多くのカトリック司祭が殺害されたということだった。そして、その話を聞いたとき、キム・スーハンは初めて、自分の意思で司祭になりたいと思った」。
この話を聞いて、キム・スーハンにとっては司祭になるということは、死を覚悟するということだったのをわたしは知った。そして、キム・スーハンにとって司祭職受諾とは、「今のこの状況の中でどうしても司祭が必要であり、自分がそれを引き受けるべきだ」ということを意味していたのだと理解できた。
独裁政権下で、人間を守るために発言し、行動したキム枢機卿の司祭職・司教職の原点にはこの覚悟と自覚があったのだと思う。それはまさに、「羊のために命を投げ出す」羊飼いとしての道であり、それこそが司祭が司祭であることの意味だと言えよう。
良い羊飼いは羊のために・・・
2008年11月24日に長崎で列福されたキリシタン時代の188人の殉教者の中には4人の司祭がいた。この司祭たちの姿も「司祭が司祭であることの意味」を考えさせる。
1597年、豊臣秀吉の命により殉教した日本26聖人殉教者の殉教録を読むと、そこには与えられた殉教のチャンスを天国の喜びにあずかるための最高の道として喜び、進んで殉教者になろうという司祭・修道者・信徒の姿が鮮明に伝えられている。しかし、1614年の徳川家康による全国的禁教令(及び、司祭と主だったキリシタン指導者の国外追放令)以降の状況の中で、潜伏司祭として生きた4人の福者司祭は、進んで殉教を求めることはなかった。彼らは日本で司祭として働くことは、最終的に殉教の死で終わるということをよく知っていた。しかし、彼らの使命は一刻も早く殉教することではなく、司祭としての姿を隠しながら、一日でも多く、迫害下のキリシタン信徒のため、そして日本人の救いのために働くことであった。
中浦ジュリアン、イエズス会司祭。1608年、長崎で叙階。1614年以降、「潜伏司祭」として日本に残り、18年間、隠れて旅をしながら、九州各地で活動。1633年、長崎・西坂で殉教。ディオゴ結城了雪、イエズス会司祭。日本に司教がいなくなったため、マニラで叙階された後、1616年に日本に潜入し、20年間にわたって、日本各地のキリシタン信徒を訪れ、励ました。1636年、大阪で殉教。トマス金鍔次兵衛、アウグスチノ会司祭。セブ島で叙階され、1631年、日本に潜入して各地で活動。1636年、長崎・西坂で殉教。ペトロ岐部カスイ。ローマで司祭叙階、イエズス会員。1630年、日本に潜入。長崎、京都を経て東北の水沢に拠点を置いて活動。1638年に江戸で殉教。
彼らは、殉教の栄冠を夢見ながらも、日々、司祭としての地道な奉仕を続けた。司祭は自分の求道のために司祭になるのではない。羊のために命をささげて生きるのが司祭なのである。
羊飼いの働き
「わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる」(ヨハネ10・11)。有名な言葉であるが、この日本語には問題もある。新共同訳が「捨てる」と訳す言葉は、ギリシア語では「ティテーミ(置く)」である。ここでは「命を捨てる=死ぬ」ということだけが考えられているのではない。必死で自分の命を守ろうとするのではなく、羊たちのためにそれを差し出すこと。イエスの場合は、実際に「命を捨てた」のだから「捨てる」という訳でよいのだろうが、これを教会の牧者にあてはめようとすれば、「捨てる」よりも「命を差し出す」のほうが適当であろう。これこそが良い羊飼いの生き方の基本である。
カトリック教会で使われている「司牧」という日本語の響きも、問題を含んでいる。「司牧」というと「司祭が信徒の世話をすること」というイメージが強い。「宣教司牧評議会」とか「共同宣教司牧」というように、日本ではよく「宣教司牧」という言葉が使われるが、この場合に「司牧」は教会の内向きの働き、「宣教」は外向きの働きを指しているようである。しかし、本来の「司牧」(パストラル・ワーク)とは教会の牧者としての働きであって、ウチかソトかは関係ない。特に貧しい人、弱っている人、助けを必要としている人のための働きを指すのが「パストラル・ワーク」である。身体的にも霊的にもその人々を助け、命に導くのが、パストラル・ワークであり、その「羊」とは決して信徒だけのことではない。「わたしには、この囲いに入っていないほかの羊もいる。その羊をも導かなければならない」(ヨハネ10・16)と言われるとおりである。
19世紀に日本に来たパリ外国宣教会の司祭たちは、人々の霊魂の来世における救済を信じ、そのために働く宣教師として極東を目指したはずである。しかし、彼らが実際に出会った病人や貧しい人を、信者であるか否かを問わずに世話していったことは、大切な牧者としての働きであった。
なお、パストラル・ワークの主体は決して司教や司祭だけでないことも忘れてはならない。教会が牧者としての働きをこの世界の中で果たすのであって、信徒も含めて教会共同体全体が、キリストの「良い羊飼い」としての働きに参加するように呼ばれている。その中に司祭の「パストラル・ワーク」もある。「司牧」は司祭の仕事であり、司祭の司牧職とは信徒の霊的な世話だけだと考えるならば、そのような司祭職理解には、根本的に偏っていると言わざるをえない。
問われていることは?
司祭の高齢化、司祭召命の減少が問題だと言われる。だが本当に「羊飼いが足りない」ことが問題なのだろうか。そうではなく、むしろ、自分が命をささげるべき羊が見えないことが問題なのではないだろうか。朝鮮戦争の中で自分の司祭職を見いだしたキム・スーハン、中浦ジュリアンやペトロ岐部には、はっきりと羊の姿が見えていたのではないか。今、ヴェトナムやミャンマーなど、司祭志願者が多い国では「飼い主のいない羊のような有様」の人々の姿がはっきりと見えているのではないか。
逆に、先進国と言われる日本のような社会(消費社会・情報社会)の中では、自分が司祭になるということが、本当に人々の救いのために必要だということが感じにくいのではないか。そういう社会では「司祭が司祭であることの意味」が見えないのだ。それが司祭召命の少ない根本的な理由であろう。
だとすれば問われているのは、わたしたちの教会が、本当に人々の救いに真剣に向き合っているかどうかということである。
第二バチカン公会議文書の『司祭の役務と生活に関する教令』6項に次のような言葉がある。「美しい儀式も盛んな会も、キリスト者としての成熟に達するよう人々を教育するものでなければ、たいして有益ではない」。そして、この箇所の註には次のようなヒエロニムスの手紙が引用されている。「壁が宝石で輝いていても、貧しい人のうちにおられるキリストが餓えているのであれば、何の役に立つであろうか」。
『神学ダイジェスト』 「上智大学神学会神学ダイジェスト編集委員会」発行
注文はリンク先を参照