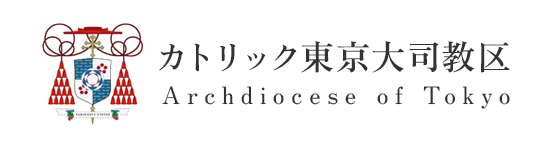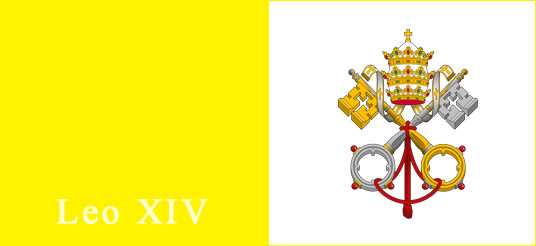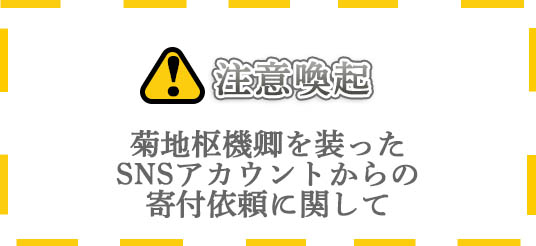お知らせ

東京教区ニュース第427号
2025年11月11日
目次
菊地功枢機卿 枢機卿名義教会着座式
 ミサ開祭直前、香部屋にて。両司教が身につけている祭服はレオナルディ教会に代々伝わるもの
ミサ開祭直前、香部屋にて。両司教が身につけている祭服はレオナルディ教会に代々伝わるもの
新たな交流の門出となることを願って
聖ジョヴァンニ・レオナルディの記念日である10月9日ローマ時間午後6時より、ローマ郊外東南東地域のトッレ・マウラ地区にあるサン・ジョヴァンニ・レオナルディ教会(以下、レオナルディ教会)にて、菊地功枢機卿の枢機卿名義教会着座式と記念ミサが行われた。
 聖ジョヴァンニ・レオナルディの像
聖ジョヴァンニ・レオナルディの像
枢機卿は名義上はローマの司祭団の一員なので、慣例によってローマ教区内のいずれかの小教区が名義教会として割り当てられる。伝統によって長年名義教会となっている小教区もあるが、レオナルディ教会が名義教会となるのは今回が初めて。枢機卿が名義教会の運営に直接関わることはないが、定期的な訪問が望ましいとされている。
 レオナルディ教会に掲げられた菊地枢機卿の紋章
レオナルディ教会に掲げられた菊地枢機卿の紋章
トッレ・マウラ地区はローマ中心部から10 kmほど離れた所にある住宅地で、主任司祭のアントニー・サミー・エスロン神父によれば、ローマの中でも比較的貧しい地区だという。歴史的な建造物が建ち並ぶ中心部とは異なって、日本の公団住宅のような集合住宅が多く、観光客の姿もない。そんな地区にあって、レオナルディ教会は日曜には4回のミサに3000人の信徒が集まる。聖堂に隣接する会館には、おもちゃが置かれたキッズルームやいくつもの卓球台がある若者のための部屋、図書館などがあり、子どものサッカーチームには100人ほどのメンバーがいる。また、コース別に分かれたカテキズムのクラスにも多くの受講者がいるとのこと。平日でも教会を訪れる信徒は絶えず、「今を活きている」共同体である。
 レオナルディ教会の周辺には集合住宅が建ち並ぶ
レオナルディ教会の周辺には集合住宅が建ち並ぶ
着座式と記念ミサには、日本からは菊地枢機卿とアンドレア・レンボ補佐司教の他、前田万葉枢機卿(大阪高松教区)、中村倫明大司教(長崎教区)、中野裕明司教(鹿児島教区)、そしてレオナルディ教会の司牧を担当する「神の母司祭修道会」出身のダビデ・カルボナーロ大司教(イタリア、ポテンツァ‒ムーロ・ルカーノ‒マルシコ・ヌオーヴォ教区)が出席。また、日本やローマからも多数の司祭が駆けつけ、6人の司教、約25人の司祭による式となった。さらに地元の信徒の他、この着座式に合わせて日本から複数の巡礼団が組まれ、ローマ在住の方々と合わせて100人を越える日本人信徒が集まった。
 ミサに集まった司教団、司祭団と
ミサに集まった司教団、司祭団と
地元の楽隊の演奏によって教会に迎えられた深紅のスータン姿の菊地枢機卿は、教会の入り口で十字架に接吻し、聖水で参列者を祝福しながら入堂、祭壇前に跪いて祈りを捧げた後、教皇儀典室のモンシニョールによって教皇による任命書が読み上げられた。香部屋にて司教団、司祭団が祭服に着替えると、一同は教会裏のサッカー場に移動し、野外にて記念ミサが行われた。
 楽隊の演奏によるお出迎え
楽隊の演奏によるお出迎え
 聖水による会衆の祝福
聖水による会衆の祝福
ミサは菊地枢機卿の主司式によってイタリア語で行われたが、説教のみ、菊地枢機卿が日本語で語った内容をアンドレア司教が一段落ずつイタリア語に通訳する形がとられた。説教の中で菊地枢機卿は聖フランシスコ・ザビエルから始まる日本における宣教の歴史に触れた後、「今日こうして、日本から多くの巡礼団がローマを訪れ、ローマにある教会共同体の皆さんと一緒にミサを捧げ、そして祈りを共にすることには大きな意味があります。それは私たちが歴史の中で、主イエスの宣教命令に忠実に働いてきたことの証しであります。困難の中にあってもくじけることなく神に従い生きることが、これほどの実りをもたらすという、希望の証しであります」と、先人たちの宣教の実りによって今の交わりがあることを述べた。さらに「いま日本の教会に日曜日に行けば、…世界中の様々な国から来られた方が、一緒になって祈りを捧げています。皆さんそれぞれ自分の個人的な理由で日本に来たと思っていることでしょう。しかし私は、そこには必ずや神様の計画があると信じています。個人的な理由で日本に来ているすべての信徒は、神様から遣わされた宣教師です。もちろん日本の教会にいるすべての人も、神様から遣わされた宣教師です。シノドス的な道を歩んでいる教会は、さまざまな方が交わって豊かにされ、宣教する教会になります」と、交わりの中にこそ日本の教会の希望があることを語った。
 レオナルディ教会主任司祭エスロン神父と
レオナルディ教会主任司祭エスロン神父と
 レオナルディ教会の聖歌隊と伴奏者たち
レオナルディ教会の聖歌隊と伴奏者たち
夕方から始まったミサが終わる頃にはあたりはすっかり夜。ミサ後には祭壇がステージに作り替えられ、若者たちのバンド演奏が行われる中、参列者たちは交流のひとときを楽しんだ。
 レオナルディ教会サッカーチームの少年のユニフォームにサイン
レオナルディ教会サッカーチームの少年のユニフォームにサイン
今回の菊地枢機卿のローマ訪問には、名義教会着座式の他、教皇一般謁見、教皇個人謁見、国際カリタス本部訪問など、複数の目的があった。その中からいくつかの場面をご紹介する。
 一般謁見で会衆に語りかける教皇レオ14世
一般謁見で会衆に語りかける教皇レオ14世
 教皇一般謁見にて、日本からの巡礼団に近づく前田枢機卿と菊地枢機卿
教皇一般謁見にて、日本からの巡礼団に近づく前田枢機卿と菊地枢機卿
 ローマ、ジェズ教会にて聖フランシスコ・ザビエルの聖遺物を崇敬する菊地枢機卿
ローマ、ジェズ教会にて聖フランシスコ・ザビエルの聖遺物を崇敬する菊地枢機卿
 国際カリタス本部にてビデオ撮影
国際カリタス本部にてビデオ撮影
 教皇庁にて、偶然出会った福音宣教省副長官アントニオ・タグレ枢機卿と語らう
教皇庁にて、偶然出会った福音宣教省副長官アントニオ・タグレ枢機卿と語らう
カテキスタの祝祭
9月26日から28日の3日間、四谷のニコラ・バレ・ハウスにて、東京教区における聖年の「カテキスタの祝祭」が行われた。
1日目は、東京教区カテキスタと日本カテキスタ会のメンバーを対象に、小西広志神父(教区生涯養成委員会担当司祭)による「カテキズムとカテキスタの歴史について」と題した講話が行われた。講話の中で小西神父は「初代教会」「古代教会」「中世の教会」「宗教改革とローマ・カテケージス」「第二バチカン公会議とその後」と時代を区切りながら、カテキズム、信仰教育の歴史について解説した。
2日目は午前の教区カテキスタ任命式の後、午後からは生涯養成委員会オープン講座第2弾「私たちを生かすミサ」の第1回目が行われ、会場いっぱいの聴衆を前にして、小西神父が「エウカリスチアの歴史」について語った。

3日目は菊地功枢機卿とアンドレア・レンボ補佐司教によるカテキスタについての対談が行われた。菊地枢機卿は仙台教区の岩手県でカテキスタを務めていたお父様の話と、司祭叙階直後から8年間派遣されていたガーナの教会におけるカテキスタの重要性に触れながら、カテキスタの働きとは何かを語った。アンドレア司教は東京教区におけるカテキスタの働きについて、特に地域ごとの小教区の特色に注目しながら解説した。
 菊地枢機卿とアンドレア司教による対談
菊地枢機卿とアンドレア司教による対談
対談の後は、菊地枢機卿司式、アンドレア司教、小西神父、小田武直神父(教区本部事務局次長、生涯養成委員会担当司祭)共同司式による祝賀ミサが行われた。ミサの説教で菊地枢機卿は神学生時代の説教学の授業で、先生(日本基督教団の牧師)が、「聖書をパッと開いてさっと開いてそこを説教できなきゃダメだよ」と言っていた思い出に触れながら、その真意は聖書の知識が頭の中に入っていなければならないということではなく、「聖書を開いた瞬間、そのみことばを通じて、神が今自分に何を語りかけているのかに耳を傾け、それを言葉にして説教するんだ」という教えだったことを述べ、イエスの教えを伝えることの本質とは何かを語った。
目黒教会国際ミサ

9月21日、目黒教会にて菊地功枢機卿司式による国際ミサが行われた。目黒教会は常に多国籍の信徒が集まる小教区であり、毎週、日本語の他、英語、インドネシア語、タガログ語でミサが行われているが、この日は普段の主日以上に大勢の、そして多国籍の信徒で聖堂はいっぱいになった。共同司式も主任司祭のアントニオ・カマチョ神父(メキシコ出身)、マーティン・デュマス神父(ガーナ出身)、協力司祭のエドウィン・コロス神父(フィリピン出身)の他、多国籍の司祭団によって行われた。
ミサの説教で菊地枢機卿は聖年のテーマである「希望の巡礼者」について、「自分が希望に満たされるというよりも、希望を多くの人に届けていくことを目指して、希望とは何なのかを考えると、希望はもののように届けることができない。……私たち一人ひとりとの出会いの中で、『あなたのことを忘れていません、共に歩いてきたんです』と伝えることによって、自分が持っている希望を証しすることによってはじめて、それを伝えていくことができます」と解説した。
ミサの後は教会の屋内外のさまざまな場所で、各国の手作り料理が振る舞われ、参加者たちを楽しませた。
 数々のフィリピン料理
数々のフィリピン料理
「貧しさ」を生きる人々
教区シノドス担当者 瀬田教会主任司祭
小西 広志神父

ひと月のあいだに2回イタリアへ行きました。そこで出会った方々のことをお話ししましょう。
9月は巡礼団の皆さんとの旅でした。美しい風景を見て感動し、各地の教会を訪れてお祈りし、美味しいものを堪能した数日間でした。ローマで巡礼団の皆さんに見ていただきたいものがありました。それは毎晩、バチカンのサン・ピエトロ広場の片隅で小さなテントの中で夜を過ごす路上生活者の方々の様子です。フランシスコ教皇さまの頃から広場の一部が夜の間開放されるようになりました。かつての郵便局はそんな人々のためのシャワー室になりました。支援のための若者たちが交代で毎晩待機しています。何よりも近くに警備の軍警察がいるので安全です。ローマ市内での路上生活はいつもいのちの危険にさらされるのです。そんな「テント村」を見せたかったので、何人かでホテルから歩いて出かけました。日中の喧騒が嘘のように広場は静寂に包まれていました。一人用の小さなテントの中には小さな灯りがありました。お邪魔をしないように静かに見てまわりました。同行した誰もが沈黙のなかで、テントで夜を過ごす方々のことを想い、祈りました。ある方のひと言がわたしのこころに突き刺さりました。「わたしの小教区の社会問題に詳しい方は、これはホームレスじゃないって言うでしょうね。なぜならテントがあるから」。わたしは情けなくなりました。あきれてしまいました。ホームレスかどうかの基準をテントの有無に求める思考があるという事実に二の句が継げなかったです。なんという硬直した貧困についての理解でしょうか?帰る家がない。帰るところがない。これは大きな哀しみです。たとえ立派なお家があったとしても、帰るところがないと感じたとき、その人は哀しみの十字架を背負って「貧しさ」を生きるのだと思います。小さなテントがあるかないかで、その人の生き方を他人が勝手に図ることはあってはならないのではないでしょうか?しかし、日本の教会の一部の方々はそんな傲慢な判断で社会を見ている。これは魂の「貧しさ」の現れです。
10月は菊地枢機卿さまに同行してローマに行きました。枢機卿としての名義教会での着座式のためです。その小教区はローマ郊外にあります。どちらかというと貧しい地域です。しかし、本当にあたたかく枢機卿さまを迎え入れてくださいました。子どもも、若者も、大人も、老人もみんなで喜んで海の向こうからやってきた高位聖職者を自分たちの仲間として受け入れてくれたのです。素朴で、しかも飾らない歓迎でした。そこにいる誰もが人生の哀しみという十字架を担っているのでしょう。誰もが「貧しさ」を生きているのでしょう。だからこそ、見も知らないわたしたち日本人を受け入れてくれたのです。「ありがたい」ことです。
そんな感激の夜が明けて、菊地枢機卿さまと一緒にサンタ・マリア・マッジョーレ教会に行きました。聖年の扉がある教会です。フランシスコ教皇さまのお墓もあります。入り口で一人の枢機卿さまと偶然出会いました。その方は粗末な椅子に座って、枢機卿の服装ではなく、ローマンカラーのシャツに古びた小さなストラを身につけていました。聞けば、毎週金曜日の午後は聖堂を訪れて希望する人々に祝福を差し上げているのだそうです。この世にはゆるしの秘跡を敬遠している信者さんはたくさんいます。願っているものの人生の哀しみゆえにご聖体を拝領できない人々もいます。そんな人々にせめてイエスさまの祝福をさしあげたいという想いからなのでしょう。
祝福を受ける人々は誰も、その方が枢機卿だとは知らないでしょう。枢機卿さまも自分が誰であるかを名乗らないでしょう。そこにあるのは人生の哀しみという「貧しさ」を仲介としたイエスさまと人との出会いなのです。ともに「貧しさ」を生きようとなさる枢機卿さまは凛とした佇まいで、清々しいものでした。キリストを生きるとはこのような姿かたちなのでしょう。
ローマ滞在中に、教皇さまの新しい文書が発表されました。「あなたがたを愛している」(黙示録3章9節)で始まるこの使徒的勧告は前の教皇さまと教皇レオ十四世とを繋ぐものであり、硬直化した貧困理解でこの世と教会を批判する人々への警告であり、すべての人々が人生の哀しみという「貧しさ」を生きるようにとの招きの書でもあるのです。
わたしたちが、「貧しさ」を多くの人々とともに歩むことができますように。

福島の地からカリタス南相馬 第46回
飯舘村長泥地区を見学して
援助マリア修道会 北村令子

5月下旬、カリタス南相馬のスタッフ研修として、福島県飯舘村の長泥地区を視察しました。飯舘村は福島第一原発事故により全村避難となった地域で、過去には村の中学生をわたしたちの修道会が運営している暁の星の研修センター(広島県福山市)に招き、交流したこともあります。
村の大半は除染が進み避難指示が解除されましたが、長泥地区だけは放射線量が高いという理由で避難指示が解除されませんでした。住民が除染を求めた際、国は「除染土を再利用する実証実験に協力すれば除染する」と提示。住民はやむを得ずそれに応じ、ようやく除染と避難指示解除が行われました。しかし、解除されたとはいえ、長泥地区には交通機関も商店も病院もなく、生活の基盤が整っていないので、帰還は無理です。新しい集会所は建てられたものの、人が集まる機会は少ないように思われます。
放射能に汚染された表土を除去するのが除染ですが、そこで出た土は中間貯蔵施設に運ばれ、その中の低線量の土を畑などに利用しようとするのが国の方針です。地中に除染土を入れ、その上に放射能汚染のない山土を50センチかぶせて農地とします。実験的に栽培された米や野菜、花などは放射線量を測定し、安全が確認されていますが、環境省の実証実験であるため、出荷は認められず、すべて廃棄されてきたそうです。元住民の農家の方々が避難先から1時間以上かけて通い、丹精込めて育てた作物が廃棄されるという事実に、怒りと悲しみを覚えました。せめて花だけでも販売できれば農家の方々の励みになるのに、と強く思いました。
今回の視察で、直接生産者の声を聞けたことは大きな学びでした。私たちの修道院は原発から20 km圏内、かつて警戒区域だった南相馬市小高区にありますが、小高の名前を出すと「小高も同じだろう」と言ってくださり、共に苦しみを乗り越えてきた者に対する共感の心を感じました。小高には電車や病院、商店があり、農業も再開が進んでいますが、長泥は復興のスタートラインに立ったばかりです。出会った農家さんたちの願いがいつか実を結ぶよう、心から祈っています。
カリタス東京通信 第27回
トー横の女の子たちと出会って
Sr.ヨルダナ(神の御摂理修道女会)
そこの女の子は一人ひとり違う。でもだいたい今までの生活では、性的・精神的な虐待、暴力を受けています。親からだったり、兄弟からだったり。自分たちが生きるために逃げるしかないとやって来る。場所は歌舞伎町、トー横。
そこは、今まではわたしにとって知らない世界でした。しかし、ちょっと関わるようになって少し知るようになりました。女の子の多くは身分証がない、着るものがない、一袋だけの荷物で、おなかがすいていて、時々治療が必要です。食べて、ゆっくり寝て、よく休むことが必要です。
はじめは「どうして逃げたのかな?家でがんばったらいいんじゃないか?」と思っていました。しかし、女の子たちが話すのを聴くと、逃げる理由もよく分かりました。
親の離婚、母親が違う男を連れてきた、自分は邪魔と言われた、父親から性的虐待を受けた、優しい言葉を聞いたことがない、頑張ったねと言われたことがない、など。こういう環境にいたらわたしも逃げたかもしれません。原因はいろいろだけど、一つにまとめるとやっぱり家族です。子どもを愛さない、大切にしない。歌舞伎町では自分が必要とされていると感じる、優しい言葉をかけてもらえる、本当の愛ではないけれど、愛されると言います。それと、お金が欲しい。優しい言葉をかけられるとついて行く。楽しい、幸せ、お金が入る。けれど裏にいろんな問題があることが分からない、お金が入るとすぐホストにあげてしまう、そうして彼女たちは夜の仕事でこころとからだを壊してしまいます。
ほとんどの子にリストカットの痕があります。最初は彼女たちがどうして傷をつくるか分かりませんでした。一度理由を聞いたら、「心の痛みよりはこの傷の方がいい」と言いました。若くて可愛い女の子は心が傷だらけです。そんな彼女たちといろんな関わりをします。時々食事を作ってあげます。簡単なものだけれど、普通の温かいごはんを。彼女たちの多くはカップラーメンの生活をしているので。ある時シチューを作ったら、「あぁ昔のおばあちゃんの味を思い出した」と言っていました。クリスマスを一緒に過ごした時に、クリスマスの歌を歌って、本当のクリスマスの意味を伝えました。簡単なプレゼントを差し上げると、「あぁ神様はほんとにいるね」とか誰かが言っていました。たまに薬を多量に飲み過ぎている子がいるとその子を見守ります。夜、一緒にいる時に、お化粧をしている子に、「しなくてもきれいですよ」というと、「お母さんの顔に似ているので、違う顔にしたいから化粧するんだ」と言っていました。
だから、彼女たちが歌舞伎町に逃げるのは、本当に幸せになりたいから逃げるのでしょう。そして、歌舞伎町の怖さを知らずに本当の怖さの中に入りこんでしまう。
一人ひとりのために祈って、神様に任せるけれど、また歌舞伎町に戻ることもある、簡単ではないですね。
だから最後はやっぱり、どんなに家が貧乏でも、どんな子どもであっても、顔がきれいとか、成績がいいとかではなくて、どんな状態であっても、親が子どもを愛すれば家に帰れるでしょう。家族は大切ですね。今の歌舞伎町の女の子は自分たちがなりたくてこうなったわけではない、犠牲者ですね。
※トー横とは「新宿東宝ビルの横」の略。
CTIC カトリック東京国際センター通信 第292号
スタッフ 奥山マリアルイサ
神様からの招待状(2)
私が彼氏(現夫)からもらった小さなチラシをきっかけに、多くのフィリピン人信徒が潮見教会の英語ミサに通うようになっていきました。
職場近くのアパートから教会に向かってぞろぞろとフィリピン人が歩いていると、日本人の配偶者になっている人、エンターテイナーとして短期間日本に滞在している人など、道すがらさまざまなフィリピン人に出会い、彼らも仲間に加わりました。その輪は口コミで広がり、フィリピン人に限らず、英語を話す他国の人たちもミサに参加するようになっていきました。ミサ後の交流の時間は、次第にそれぞれが抱えている問題を分かち合ったり、神父様やJOC(カトリック青年労働者連盟)の人たちに相談したりする場にもなって行きました。
日本人のO神父様は英語が話せなかったので、何かあるとすぐに私に通訳を求めます。私は日本語で十分にコミュニケーションがとれる状態ではなかったのですが、神父様はおかまいなしに私に通訳をさせるので、私も一生懸命日本語を勉強しなければならないと思うようになりました。特に、労働問題に関する言葉や日本の制度を学ぶ必要があると意識するようになったのはこの頃です。
年月が過ぎ、一緒に工場で働いていた同僚たち、レイミッショナリー、そして外国人の神父様たちがそれぞれ祖国に帰国し、教会の様子も変わっていきました。
ある日、O神父様から驚きの発表がありました。「来月から英語のミサを止め、その代わりに、聖歌や聖書朗読に外国語を交えたミサ(インターナショナルミサ)を行うようにします」。私はそのお知らせにショックを受けました。その頃には、ミサに参加していた初期メンバーの多くは帰国し、残っている人たちは日本人等と結婚するなどしてある程度日本の生活に馴染んでいました。新しく来る人たちについては、古い人たちがお世話をするようになっていました。私も日本人の配偶者となり、二人の子どもを持つ母親になっていました。
日本語のミサはよくわかりませんでした。しかし、これからも日本で生き、子どもを信仰面で導くために、み言葉を日本語で聞くことは大切なことだと思ったので、一度のミサで一つの単語でも神様の言葉を日本語で持ち帰ろうと決心し、参加するようにはしていました。それでも時には英語やタガログ語のミサが懐かしくなり、他の教会の英語ミサに参加することもありました。小さな娘を連れ、都内の大きな教会の英語ミサに参加した時のことです。ミサの後、娘が「マミー、この教会イヤだ。怖い。もう来たくない」と言ったのです。理由を聞くと、「大きな教会に沢山の大きな人がいて、周りが見えないし、ミサの後、みんな、お話もしないでそのまま帰るから怖い」と言うのです。その言葉を聞いた時、私は子どものためにも「自分の小教区の日本語のミサを自分と家族の中心にする」ことを決心し、積極的に参加するようになりました。振り返ると、自分の小教区の方々との交流を通して、季節のこと、子育てのこと、日本の教育のこと、料理のこと、健康のこと、社会制度のことなど、多くのことを学ぶ道が開けていったと思います。
私がカトリック東京国際センターのスタッフとして働くようになり17年が過ぎようとしています。
1989年に受け取った英語で書かれた小さなチラシは、今の人生への「神様からの招待状」だったと感じています。
カリタスの家だより 連載 第177回
子どもたちが照らす先に
放課後等デイサービス カリタス翼 管理者 向井 崇
この夏休み、放課後等デイサービス 「カリタス翼」の活動として、子どもたちと一緒に公共交通を使って映画館に出かけました。初めて家族以外と電車で外出する子も多く、事前にイラストや写真で流れを示して準備を整えたことで、みんな落ち着いて出かけることができました。映画館では笑顔いっぱいに映画を楽しむ姿がありました。
そのとき参加された子どもの一人は、これまで公共交通をほとんど利用したことがありませんでした。過去にお母さんが一人でバスに乗せた際、その子がパニックになり、以来、家族での外出はお父さんの車が中心になっていたのです。泣き叫ぶ我が子を前にした無力感や、周囲からの冷たい視線を思うと、二度と公共交通を利用したくなくなる気持ちは想像に難くありません。
自閉症は決して「閉じている」わけではありません。その人、その子なりに他者とかかわろうとしています。ただし感覚の特性やコミュニケーションの難しさから、周囲には理解しにくい行動として映ることがあります。バスの騒音やアナウンスの刺激、先の見通しの立ちにくさなど、理由があっての反応なのです。
それにもかかわらず、社会はしばしばその背景を理解しようとせず、驚き、冷たい視線を向けます。実際にはご本人にとっての理由が積み重なっているのですが、周囲からは見えにくい…。そのすれ違いが、ご本人やご家族をさらに追い込んでしまいます。マザーテレサが語った「愛の反対は憎しみではなく、無関心」という言葉の通り、自閉症の人たちを「閉じ」させているのは、むしろ私たちの側なのではないでしょうか?
現在、自閉症と診断される人が増えています。かつて(僕が大学生だった30年前)は440人に1人(0.23%)とされていたのが、今では100~40人に1人(1~2.5%)が自閉症と診断されています。しかしこれは、自閉症という存在が急激に増えたというよりも、診断基準の変化や理解の広がりによる部分が大きいと考えられます。自閉症スペクトラムとは、虹のように幅広い特性の「連続性」であり、診断を受ける人もいれば、診断の必要がなく社会の中で穏やかに暮らしている人もいます。つまり「増えた」のではなく、これまで「普通」とみなされていた人の中からも、実は支援を必要とする人が見えてきたといえます。換言すれば、社会が「普通」の基準を狭め、そこからこぼれ落ちる人が増えてきたともいえるのです。
僕は2017年1月の教区ニュースで「我が事として」と題し、相模原の津久井やまゆり園事件について触れました。社会の排他性と私たち自身の利己的な心が、障害のある人を囲い込み、結果として悲劇を招いたのではないかと考察しました。あれから10年近く経ちましたが、社会の分断や、通常から外れる人への排除は、むしろ強まっているように感じます。「勝ち・負け」「普通・異常」「日本人・外国人」といった二項対立をあおる言葉が、かえって注目を集めるような社会になってはいないでしょうか?
戦後日本で「社会福祉の父」といわれた糸賀一雄さんは「この子らを世の光に」という言葉を残されました。今回の映画館での体験は、子どもたちが安心して地域に出ていく一歩となりました。子どもたちが世を照らす光となるとき、その光が照らし出す社会がこれから少しでも温かく包み込むものであることを、僕は強く願っています。
編集後記
蒔かれた種が
いつ咲いていつ実るのか
それは誰にも分からない
私たちにできるのは
ひたすら信じること
何十年も前の種が
明日に満開の花を咲かせる
そんなこともあるはずだから(Y)