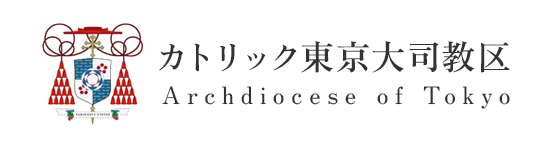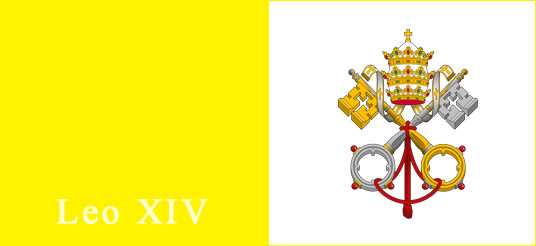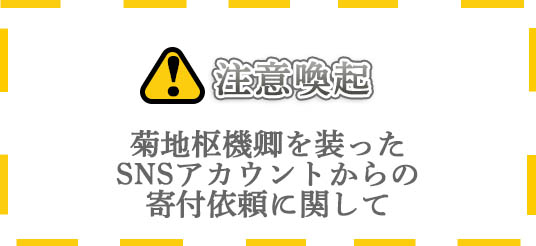お知らせ

東京教区ニュース第421号
2025年04月01日
目次
ようこそ東京へ!ミャンマーから司祭2人が来日
 左からカシミロ神父、菊地枢機卿、ヘンリー神父。枢機卿の手にはニコラス司教から贈られたロザリオ
左からカシミロ神父、菊地枢機卿、ヘンリー神父。枢機卿の手にはニコラス司教から贈られたロザリオ
3月10日深夜、東京教区の姉妹教会であるミャンマーの教会から、2人の司祭、ヘンリー・アウン・ゾーウー神父とカシミロ・アイソー・ロン神父が羽田空港に到着した。2人はミャンマーの「聖テレーズの小さな道宣教会(LWMT)」の所属。LWMTから東京への司祭派遣は7年前から協議が続けられていたが、コロナ禍で来日が困難となっていた。コロナ禍も一段落し、今年1月のアンドレア・レンボ補佐司教によるミャンマー訪問の際に面談等の最終確認が行われ、ようやく来日が叶った。 今回が初来日である2人は、まずは日本語学校で日本語を学び、その後、東京教区のために働いていただく予定。東京とミャンマーの友好の実りである2人の司祭の新しい歩みを、皆様のお祈りによって支えていただきたい。
※聖テレーズの小さな道宣教会(Littel Way Missionary of St. Therese)について
1999年にマンダレー教区のニコラス・マン・タン大司教とアイルランド出身のメアリー・ドゥーハンさんによって共同設立された。会の名称はリジューの聖テレーズの思想である「小さき道」による。「小さなことを大きな愛で」を会の霊性に、「イエスを広く知らしめ、愛してもらう」を会のビジョンに定めている。メンバーは司祭24人と助祭1人。
 築地教会にて。左から、ヘンリー神父、ヴィンセント神父、カシミロ神父、レオ神父
築地教会にて。左から、ヘンリー神父、ヴィンセント神父、カシミロ神父、レオ神父
ヘンリー神父&カシミロ神父インタビュー
東京教区の皆様にヘンリー神父とカシミロ神父のことを知っていただくために、お2人に生い立ちから召命や趣味まで、詳しく答えていただいた。このインタビューを通じて2人の司祭を身近に感じていただければ幸いである。
◉ヘンリー神父
─簡単な自己紹介をお願いします。
ヘンリー神父 ミャンマー、タウンジー大司教区のヘンリー・アウン・ゾーウー神父です。「聖テレーズの小さな道宣教会」に所属しています
─生まれたのはどんなところですか?
ヘンリー神父 シャン州南部、ピンラウン郡区のナウンタヤーで生まれました。住民のほとんどはパオ族で、彼らは熱心な仏教徒です。その中で唯一カトリックの家族があり、それが私の家族です。
─どのような子ども時代を過ごしましたか?
ヘンリー神父 地域の皆が仏教徒の中、唯一のカトリック家庭だったので、私たちは人間関係、宗教、教育、経済等、あらゆる面で差別されていました。なので、過酷な幼少期を過ごしたと言えるでしょう。
─なぜ司祭になろうと思ったのですか?
ヘンリー神父 「もう1人のキリスト(Alter Christus)」になることが私の子どもの頃からの夢でした。それで、私は司祭になることを決意しました。
─なぜ日本に来ようと思ったのですか?
ヘンリー神父 ニコラス・マン・タン大司教(マンダレー大司教区名誉大司教、聖テレーズの小さな道宣教会共同創立者)は、東京大司教区がミャンマーの教会を様々な形で、特に経済的に支援していると言っていました。そして、その恩返しに東京大司教区のために何かできることをしたいと願っていました。 その願いは、タルチシオ菊地功枢機卿、アンドレア・レンボ補佐司教、そして東京大司教区の司祭の皆様、特にレオ・シューマカ神父(コロンバン会)、ラズン・ノーサン・ヴィンセント神父(ミラノ外国宣教会)が、私たちを司牧者として東京大司教区に受け入れ、歓迎してくださったことで叶えられました。
─日本の印象は?
ヘンリー神父 キリスト教が長い迫害の時代を生き抜き、宣教師と現地の教会の両方によって宣教活動が行われてきたことに感銘を受けています。
─趣味と好きな食べ物を教えてください。
ヘンリー神父 趣味はサッカーと釣りで、好きな食べ物はカヤンの伝統料理です。
─好きな聖書のみことばを教えてください。
ヘンリー神父 「沖に漕ぎ出し(なさい)」(ルカ5章4節)
 築地教会にて、東京のミャンマー共同体での初ミサに臨むヘンリー神父(右)とカシミロ神父
築地教会にて、東京のミャンマー共同体での初ミサに臨むヘンリー神父(右)とカシミロ神父
◉カシミロ神父
─簡単な自己紹介をお願いします。
カシミロ神父 カシミロ・アイソー・ロン神父です。司祭として、「テレーズの小さな道宣教会」に所属しています。司祭になって7年になります。現在40歳です。シャン州南部のペコン郡区にあるター・オーク村の出身で、カヤン族に属しています。3人の姉と1人の妹、1人の弟がいます。
─生まれたのはどんなところですか?
カシミロ神父 私はター・オークという貧しい村で生まれ、とても貧しい家庭で育ちました。村の他の家庭も皆貧しく、教育を受けていませんでした。村人全員が貧しく無学であるのを見るのはとても悲しいことでした。生計を立てるために、彼らは農作業をすることしか知りませんでした。そして教育の価値を理解していなかったため、子どもたちに教育を受けさせることにもあまり関心を持っていませんでした。私自身、自分が教養のある人間になるのはとても難しいと感じていました。
─どのような子ども時代を過ごしましたか?
カシミロ神父 私は農民である両親のもとで育ちました。悲しいことに、私が5歳のときに母が腎臓病で亡くなりました。母の死後、父は家族を支えるためにとても苦労しました。家族が生き延びるために、父は多くの困難に直面しました。さらに、3人の姉は父を助けるために働きに出なければなりませんでした。その結果、姉たちは皆、学校に通って教育を受ける機会を失ってしまいました。
─なぜ司祭になろうと思ったのですか?
カシミロ神父 私の祖父と父はどちらもカトリックのカテキスタでした。彼らは私にとって最初に影響を与えてくれた人物であり、私の司祭召命にも大きな影響を与えました。父は私が子どもの頃から、司祭になるよう励ましてくれました。私はその励ましを受けて育ちました。ですから、最初に司祭になろうと思ったのは自分の意志ではなく、段々と、司祭になりたいという自分の意志に気づくようになりました。私が司祭になりたいと思ったもう一つの理由は、私の村から司祭が出ていないという認識でした。その気づきは私に大きな感動を与え、司祭になるための強い刺激となりました。実際、私は自分の村で初めての司祭になりたいと思っていました。
─なぜ日本に来ようと思ったのですか?
カシミロ神父 正直に言うと、私の人生の中で、いつか日本へ宣教に行く日が来るとは思ってもみませんでした。私が日本に行きたいと思うようになったのは、ニコラス・マン・タン大司教から、日本への宣教を提案されたときです。私はその提案に驚き、断ることができませんでした。
─日本の印象は?
カシミロ神父 誰もが知るように、日本はその発展、美しい場所、体系的な政策、清潔さ等によって、多くの外国人を引き付ける素晴らしい国です。外国人として、私は率直に日本に対して非常にポジティブな印象を持っています。
─趣味と好きな食べ物を教えてください。
カシミロ神父 スポーツではサッカーとチンロン、そしてオルガンやピアノ、ギターを演奏することが趣味です。好きな食べ物はご飯とスパゲティです。
※チンロン:ミャンマーの伝統的な球技で、選手たちが足で籐でできたボールを落とさないように蹴り続ける。日本の蹴鞠にも似ている。
─好きな聖書のみことばを教えてください。
カシミロ神父 「哀れな人を守ってくださる主は 弱り果てたわたしを救ってくださる。」(詩篇116編6節)
今井克明神学生朗読奉仕者選任式ミサ
 菊地枢機卿の訓話に耳を傾ける今井神学生
菊地枢機卿の訓話に耳を傾ける今井神学生
2月9日午後、東京教区一粒会総会の日に合わせて、東京カテドラル聖マリア大聖堂にて菊地功枢機卿司式による、東京教区神学生今井克明さんの朗読奉仕者選任式ミサが行われた。
ミサの説教で菊地枢機卿は「(朗読奉仕者の務めは)第一に、典礼祭儀で神の言葉を朗読し、第二に教理を教えて秘跡に与る準備をさせ、そして第三にまだキリスト教に出会っていない人たちに救いの教えを知らせることであります。すなわち朗読奉仕者とは典礼において上手に朗読をするだけの奉仕者ではなく、まさしく福音を告げ知らせ、教会の教えを伝えるために特に選任される重要な役割です」と朗読奉仕者の役割について説き、「福音宣教は、単に言葉で語るだけではなく、行いによるあかしをもって伝えられなければなりません。具体的な出会いをもたらす者でなくてはなりません。空虚なことばを語る者ではなく、行いによるあかしとして最も大切な愛の奉仕のわざに生きる者であってください。希望を生み出す出会いをもたらす者であってください」と今井神学生を激励した。
司祭団が退堂する際、大きな拍手で今井神学生を祝福する会衆に対し、立ち止まってはにかんだ笑顔で手を振り、会衆に応える今井新学生の姿が印象的であった。
 会衆の拍手に手を振る今井神学生
会衆の拍手に手を振る今井神学生
キリストとの出会いの助けとなるように
東京教区神学科2年
アンセルムス 今井克明
いつも私たち神学生のためにお祈りいただきありがとうございます。
2025年3月9日の東京教区一粒会総会に合わせて東京カテドラル聖マリア大聖堂において行われたミサの中で、菊地功枢機卿さまより朗読奉仕者の選任を受けました。ミサに出身教会の高輪教会や、秋津教会や町田教会のように司牧実習(神学院の学期中の主日や、長期休暇中に特定の小教区に滞在し、司牧と司祭の生活について学ぶこと)で私を受け入れてくださった教会、さらに東京教区の多くの教会からお集まりいただいたこと、またそれぞれの教会やご自宅などから心を合わせてお祈りいただいたことに心より感謝申し上げます。
この度、私の受けた朗読奉仕という務めは、「典礼集会において神のことばを朗読し、子どもや大人に教理を教えて秘跡に預かる準備をさせ、まだキリスト教を知らない人に救いの教えを知らせ」るものであるとされています。選任式ミサが始まると、改めてこの務めの重大さを痛感し、私が誰かに何かを教えることができるだろうか、荷が重いのではないだろうかと心を騒がせていました。そうこうしている内に名前が呼ばれ、「はい」と応え、内陣に上りました。声は平静を装ったつもりですが、やはり緊張したまま朗読台の近くに置かれた椅子に座り、私のすぐ目の前で話される菊地枢機卿さまの説教を聞いていました。その説教の中で枢機卿さまは、教皇ベネディクト16世の回勅『神は愛』を引用しながら、「キリスト者をキリスト者たらしめているものは倫理的な選択や高邁な思想」にあるのではなく、「ある出来事との出会い、ある人格との出会い」にあると仰いました。私はそれを聞いて、やっと朗読奉仕という務めが知識を「教えてあげる」ものではなく、みことばを読み、みことばに親しみ、自らの内にみことばが生きるように生きていくという教会の務めを特別に引き受けるとともに、全てのキリスト者が持ち、また求めるみことばとの親しさをより一層深いものとするように支えるという奉仕を引き受けることであると実感しました。それは私とみことば、すなわちキリストとの出会いを、言葉を含めた生き方を通して、出会う全ての人とキリストとの出会いの助けとなるよう仕えることではないか、と今は考えています。
それでも、その務めを果たしていくことは、自分の弱さを知っている私にとって相変わらず難しいことです。しかし神が求めているのであれば、まず神の助けによって、そしてまた多くのお祈り、と言っても個別具体的困難に対してというより、私が苦しい時に祈ってくれている人がいると信じさせてくれる皆さんによって、この務めを引き受けていけると信じています。どうか弱い神学生のために、今後ともお祈りいただければ幸いです
 菊地枢機卿から聖書を授与される今井神学生
菊地枢機卿から聖書を授与される今井神学生
やさしいことば
教区シノドス担当者 瀬田教会主任司祭
小西 広志神父

昨年の12月、菊地功枢機卿さまの親任式に同行させていただきました。親任式では新枢機卿と秘書の服装の規定が厳しく定められています。枢機卿は、いわゆるカーディナル・レッドと呼ばれる緋色のお召し物を身につけなければなりません。靴下のお色まで決まっています。秘書も規定によればスータンを着用となっています。普段、薄汚れたフランシスコ会の会服を身につけているわたしも、生まれて初めて教区司祭と同じようにスータンに袖を通しました。
親任式の当日、続々と新枢機卿さま方が控えの間に集まってきました。その中でドミニコ会のティモシー・ラドクリフ枢機卿さまはドミニコ会の白の会服を身につけておられました。居ならぶ枢機卿さま方の中で異彩を放っておられました。そしてよく見ると、会服の下に身につけておられるズボンはデニムでした。決して上等ではないくたびれたデニムのズボンとこれまた履き古したスニーカーのような靴をお召しになっていました。会服と普通のお召し物。これがラドクリフ枢機卿さまのアイデンティティーを表すものなのでしょう。気張るわけではない普通のおこころと修道会の伝統に支えられて、枢機卿さまは教皇さまの前にひざまずき、枢機卿の指輪と帽子(ビレッタ)を頂いていました。他の方々が緊張しているにも関わらず、ラドクリフ枢機卿さまはいたって普通でした。
聖ドミニコは説教が上手だったと言われています。しかし、その説教は残っていません。彼は当時、異端の疑いをかけられ、霊的にも迷いのあった修道女たちを助けました。修道者としての本来あるべき姿へと導きました。どんなお話を聖ドミニコは彼女たちにしたのでしょうか。もちろん神さまとイエスさまについてのお話だったでしょう。しかし、どんな口調で、どのようなことばを選んで、霊的に道を外れそうになっていた修道女たちに語りかけたのでしょうか。おそらく彼女たちが解る、受けとめることのできることばで語ったのでしょう。
ティモシー・ラドクリフ師は2024年と2025年に開催されたシノドス(世界代表司教会議)第16回通常総会で、霊的な指導者として参加者たちに語りかけました。会期中、毎日のように説教をなさいました。300名を超える参加者たちのこころを、「シノダリティ」の教会の方へと向けたのです。決して、厳しいことばを語ることなく、分かりやすいことばで語りかけました。こうして彼は「シノダリティに関するシノドス」の脇役の務めを担ったのです。教皇官邸の公認の説教者であったラニエロ・カンタラメッサ枢機卿とは全く違う語り口で、ラドクリフ師は語り続けました。
それは、ほんとうにやさしいことばでした。誰かを批判するわけでもなく、誰かを否定するわけでもない。それでいて、こころにしみこんでいくことばの数々は、聞くものに回心をうながし、教会への愛を呼び覚ますものでした。
ラドクリフ枢機卿さまは、日常をしっかりと生きているのだと思います。背伸びをして神さまをのぞき込むのでもなく、小さい自分のところにイエスさまを落としこんでしまうのではない。周りの人々と兄弟姉妹として生きる、とりわけ霊的に迷い、道を外れそうになっている人々とともに生き、歩むという姿勢が、やさしく分かりやすいことばに表れているのです。
やさしいことばは、ラドクリフ枢機卿さまだけではないようです。それは教会に満ちつつあります。「日本にやって来た総本部の視察者たちが、とてもやさしくなりました。以前はどことなく高圧的で、『べき』論をふりかざしていましたが、今は、このどうしようもない日本のシスターたちに寄り添うようなことばをかけてくれます。そして、実際に寄り添ってくれます」という評判を時々耳にするようになりました。分かりやすく、やさしいことばを語ることで、相手とともに生きていこうとするあり方は、教会の特徴となっているのでしょう。つまり、「シノドス的」な教会はすでに始まっているのです。2021年から明確に始まった「シノダリティ」を目指す教会の歩みは、少しずつ実りをもたらしているのだと思います。やさしいことば、そして人との交わりの体験。これらはわたしたちを神のいのちへと導いてくれるのです。
※ティモシー・ラドクリフ師(ティモシィ・ラドクリフ)の著作は日本語でも3冊ほど発売されています。また、シノドス 第16回通常総会での講話はカトリック中央協議会のサイトで見ることができます。
菊地枢機卿、袴田巌さんを訪問 ―教皇庁からの手紙とロザリオを携えて―
 前列左から門間さん、袴田巌さん、後列左からひで子さん、菊地枢機卿
前列左から門間さん、袴田巌さん、後列左からひで子さん、菊地枢機卿
ローマ教皇庁は、殺人のえん罪で死刑判決を受け、昨年10月9日に再審による無罪が確定した袴田巌さんに祝福の手紙と教皇紋章入りのロザリオを贈った。手紙は教皇フランシスコの指示により、教皇庁国務省総務局長エドガル・ペーニャ・パラ大司教によって書かれたもの。手紙とロザリオは今年1月、袴田さんにお渡しするようにと教皇庁大使館を通じて、司教協議会会長である菊地功枢機卿に託されていた。
これを受け、今年の2月22日、菊地枢機卿は手紙とロザリオをお渡しするため、静岡県浜松市の袴田さんの自宅を訪問した。面会の席には袴田さんの姉であるひで子さんと「無実の死刑囚・袴田巌さんを救う会」副代表の門間幸枝さん(清瀬教会信徒)が同席した。手紙には「教皇は袴田さんの無罪判決を聞いて喜び、袴田さんの苦しみが霊的な果実を結ぶことを信じている」と書かれており、ロザリオはひで子さんの手によって袴田さんの首にかけられた。
菊地枢機卿との会話の中でひで子さんは、「58年間も闘ってきたのだからこれで終わりということはない。これからもえん罪で苦しんでいる人のために活動し続けたい」とさらなる決意を述べた。
※「袴田事件」とは
1966年に静岡県で発生した一家4人殺害事件で、元プロボクサーの袴田巌さんが逮捕・有罪判決を受けた事件。袴田さんは、証拠が不十分な中で自白を強要されて死刑を求刑され、1980年に最高裁で死刑が確定。しかしDNA鑑定等新たな証拠が出たことで2014年に死刑と拘置の執行が停止され釈放。2023年3月に再審が開始。2024年10月、物的証拠や自白調書の捏造が認定され、無罪が確定した。袴田さんは1984年に故志村辰弥神父(東京教区)により洗礼を受けている。洗礼名はパウロ。
 教皇紋章入りロザリオを首にかける袴田さん
教皇紋章入りロザリオを首にかける袴田さん
パウロ袴田巖さんの再審完全無罪を迎えて
無実の死刑囚・袴田巌さんを救う会
副代表 門間幸枝
2024年10月9日は私にとっても善を持って悪に勝った日でした。袴田巌さんが再審無罪を得るまで58年の年月を要しました。長い間、お祈りと温かいご支援を頂きました皆さまに心から感謝を申し上げます。本当に、本当にありがとうございました。
2025年の元旦、ある支援者から届いた賀状に「新年明けましておめでとうございます。でも本当に心からおめでとうと言えるようになっていません。心から言える2025年にしましょう」とありました。私はびっくりしました。理由は違うかもしれませんが同じ気持ちだったからです。私はすでにそのことを「キリスト者平和ネット」のニュースレター昨年の11月号に告白していました。パウロ袴田巖さんが完全無罪となった2024年10月9日は『えん罪撲滅の日』にして、忘れてはならない日にしてほしい。国民一人ひとりが自分のこととして年に一回は考える日になれば、えん罪のない国に近づけるのではないか……と。
そして2月5日には、平和をつくる宗教者ネットの皆さんと共に内閣府に参り、次のような請願書を提出しました。
無実の死刑囚・袴田巖さんの再審完全無罪が確定した日は、昨年の十月九日でした。この日を「えん罪撲滅の日」として、国民の一人ひとりが、年に一度でも、えん罪について考えるよう、学ぶことができるよう定めて下さい。
再審制度見直しで一致した超党派議連が、今国会に改正案を提出すると報道されました。(東京新聞一月二十九日) 善は急げと申します。一日も早く実効性と中味のある改正を成立させてください。心から請願致します。
門間幸枝
内閣総理大臣 石破 茂 様
そして、キリスト教非戦平和誌「友和」第751号(1・2月号)にもこのテーマで書かせていただきました。 2025年2月17日現在、超党派の国会議員による「えん罪被害者のための再審法改正を実現する議員連盟」は、衆参計373人の議員が名前を連ねています。
戦争と死刑、そしてえん罪に加担する人たちは人間の尊厳を失った人たちであり、真実に弱い人たちに見える。だから私たちは、絶えず真実を求め、疑問があったら、どこまでも追求し、真実の前に正しく強くなければなりません。フランスの思想家モンテーニュは「無実者を罰することは、犯罪事実よりも犯罪的である」と述べています。聖書には、「幼な子でさえも、その行いによって自らを示し、そのすることの清いか正しいかを表わす」(箴言20-11)とあります。
「悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい」(ローマの信徒への手紙12・21)この聖句に支えられて、39年目にこの日を迎えることができました。「無実の死刑囚・袴田巌さんを救う会」はこの3月で解散になりますが、門間ゴスペルファミリーのヒューマンライツメッセージコンサートは続きます。キリストにある新しい生活によってえん罪撲滅の世界をめざしながら、再審法改正・死刑制度の廃止等に少しでもお役に立てれば幸いです。
「聖書に出る『悪』とは、人が人を抑圧している状態を表すことばということを、忘れてはならないと思います」(本田哲郎訳「小さくされた人びとのための福音(上)」より)
 袴田家の愛猫ルビーちゃんと。ルビーちゃんは袴田さんが家で寂しくないように保護団体から引き取られたとのこと
袴田家の愛猫ルビーちゃんと。ルビーちゃんは袴田さんが家で寂しくないように保護団体から引き取られたとのこと
2024年~2025年 生涯養成委員会 「オープン講座」の経過のご報告
昨年秋に、東京教区として初の試みとなる信徒および奉献生活者を対象としたカテキズムを学び直すための「オープン講座」が始まり、半年が経過しました。生涯養成委員会では7年前の2018年に信徒カテキスタの養成を開始し、翌年には26人のカテキスタが誕生。その後も養成は続き、第6期を終えた現在、約40名のカテキスタが葛西・清瀬・関口・関町・築地・西千葉・松戸の計7か所の小教区に派遣され、入門講座やフォローアップ講座を行っています。
昨年も9月から始まる第7期の受講者を募ったものの、応募者が少なかったため、準備した講座を急遽一般公開に切り替えて実施することといたしました。毎月第2・第4土曜日の午後に、四ツ谷駅前のニコラ・バレ・ハウスの9階ホールを拝借し、講座内容は基本的に『カトリック教会のカテキズム』に沿った構成で全22回と、これまでのカテキスタ養成プログラムと変わりませんが、派遣先での実際の講座を想定した模擬授業を行う代わりに、講師による講義形式のみとしました。その分、講師の方にはこれまで以上に時間をかけた丁寧な講義を行っていただいています。また、毎回、講義の後に受講者の方々からのご質問をお受けしており、活発な質疑応答がなされています。
 会場いっぱいの参加者たち
会場いっぱいの参加者たち
今回の講座の開始時点では、どのぐらいの人数が受講されるのか想像もつきませんでしたが、初回からほぼ一定して会場の定員100名がちょうど満席になる状態が続いています。受講の申込は不要ですし、お名前や所属教会もお尋ねしないことにしましたので、どのような方が受講されているのか分かりませんが、中にはかなり遠方からお越しの方もおられるようです。 当初、スケジュールを見て興味のあるところだけ受講される方がおられるのでは、と思っていましたが、実際には毎回ほぼ同じメンバーが来られていて、通しですべての講座を受講される方が多いように思います。これだけ多くの方がカテキズムを学び直されたいと来られたことに、はじめは驚きをもってお迎えしたのですが、今では、残りの半年間、できる限り受講する方々のご要望に沿った形で運営できればと、身が引き締まる思いです。
現在、オープン講座はちょうど折り返し地点を迎えています。昨年10月以降、東京教区の猪熊太郎師、髙木賢一師、サレジオ修道会の阿部仲麻呂師、フランシスコ会の小西広志師をお迎えして、『カトリック教会のカテキズム』の「第1編 信仰宣言」に相当する部分を終え、4月からの後半は、猪熊師、髙木賢一師に加え、東京教区の高木健次師、古市匡史師、信徒の赤井悠蔵氏により、「第2編 キリスト教の神秘を祝う」以降の内容を学んで行くことになります。 カテキスタの養成と同じ内容なら自分には難しすぎるのでは?とお思いの方がおられるかも知れませんが、講師の方々はわかり易く丁寧な講義をなさいますので、決してそのような心配はないと思います。後半だけでも受講してみようかな?とお思いの方も歓迎いたしますので、どうぞご参加ください。お待ちしております。 尚、講座のスケジュールなど、詳しくは教区HPの2024年7月29日付のお知らせをご覧ください 。
 髙木賢一神父による講話
髙木賢一神父による講話

CTIC カトリック東京国際センター通信 第286号
50年ほど前にパスポートと外国人登録証を失くし、「日本人のように」生きて来た金さん(仮名)。日本に来る少し前に親が本籍地を移転していたため、本籍地の住所もはっきりしないうえ、親族との連絡も途絶えてしまっている。そんな金さんが、「韓国人のオーバーステイの金」として入管に出頭し、韓国に帰国するためには、それを証明する書類が必要でした。まずは領事館に相談するしかないのですが、多忙を極める領事館の窓口で韓国人であるかどうかわからない金さんの事情を聞いてもらうためには、日本で生まれてから現在に至るすべてのことをできるだけ具体的に記し、彼の話に信憑性を持たせる必要がありました。「大阪の〇〇町の××会社の3軒隣に住んでいた」「大人になって日本に戻って来たのは羽田空港。その日の晩に△△駅に住む父親の知人と焼肉を食べ、翌日新幹線で大阪に向かった」など、金さんは記憶力がとてもよく、その情報量は膨大なものでした。それらの記憶を日本語でまとめ、西千葉教会の金泌中(キム・ピルジュン)神父様に韓国語に訳していただき、東京韓人教会の方に手伝ってもらって韓国大使館に相談をし、アドバイスをもらいました。同時に金さんの戸籍があると思われる韓国の役所や地方公共団体に片っぱしから国際電話をかけ、手掛かりを探しました。韓国と連携のある労働組合や、日韓交流を行っている団体、修道会、大学の先生方まで、当たれるところはすべて当たってみるしかありませんでした。
高齢のお二人ですので、国際電話をかけるために事務所に来ていただいたり、弁護士事務所に相談に行ったりするのも毎日というわけにはいきません。体調を見ながら、無理のないスケジュールで右往左往しているうちにどんどんと時間が過ぎて行きました。その間にも、血圧が上がったり、血尿が出たりと受診が必要になったお二人が無料低額診療で受診できる病院につながるまでの間、カトリック信者のドクターが手を差し伸べてくれました。
3週間の約束で受け入れていただいたベタニア修道女会での生活が6カ月を過ぎ、これ以上無理を言えなくなった時には、麹町教会の「あしたのいえプロジェクト」が「シェルターに空きが出ました」との連絡をくださり、何とか滞在場所を確保することができました。すべてが綱渡りの毎日でしたが、多くの方が関われば関わるほど、絶望の中で一度は死を覚悟したお二人は「どうして皆さんがこうもよくしてくれるのですか?」と、その出会いを喜んでいました。
9月末のある日、金さんが思い出した韓国のとある住所に関係する、地域の相談窓口の方との電話での会話の中で、金さんは遂に本籍地を突き止めることができました。偶然の出来事でしたが、帰国の可能性が見えた最初の瞬間でした。
大喜びしたものの、次はその本籍地にある書類そのものを入手しなければなりません。本人の身分証がないので郵送で申請することができず、また、その方法を探らなければなりませんでした。再度試行錯誤を繰り返した末、韓国カトリック議政府教区の外国人支援センターの特別な権限を持ったスタッフの協力により、それが金さんの手元に届くまで、更に1カ月の時間が必要でした。
金さんとCTICが出会って7カ月が経過した11月初旬に「韓国人の金さんであることを証明する書類」を手に、金さんと内縁の妻の朴さん(仮名)は晴れて(?)入管に出頭することになりました。(続く)
 お二人を最初に受け入れた病院からCTIC運営委員長の菊地枢機卿に感謝状が贈られた
お二人を最初に受け入れた病院からCTIC運営委員長の菊地枢機卿に感謝状が贈られた
カリタスの家だより 連載 第171回
ボランティア養成講座のお知らせ
春夏秋冬のある国に生まれた私たちは、四季の恵みを当然のように受け止めて参りました。春や秋が忘れられてしまったかのようなこの数年を思うにつけ、この世には永遠に続くものはなく、季節ですら変わっていくのだと感慨を深めます。やはり永遠はただおひと方のものなのですね。
現在、わが国は65歳以上の人口が20%を超える「超高齢社会」を迎えています。幼児、少年少女、青年、壮年、老年という人口のバランスが崩れようとしています。ボランティアはこの現実を避けては通れません。
今年度のボランティア養成講座は、高齢社会にボランティアが正しい知識と柔軟な対処、何より温かい寄り添いをもって臨めるよう下記のとおり企画いたしました。誰もが迎える「老い」が穏やかで豊かなものとなることは、すべての世代の関心事ではないでしょうか。 各方面からの講師によるレクチャーと質疑応答、参加者同士の実感やご意見の交換が、皆さまの今後の活動の支えになることを、そしてひとりでも多くの方にご参加いただけるよう願っております。
ボランティア養成講座 実行委員長
西村 真理
参加費=各講座 1,500円
時間=各回13時開始 16時終了予定
申込期間= 4月15日より受付開始
申込方法 =電話 03-3943-1726(月曜~土曜10時~14時) もしくはこちらのフォームから
2025年度ボランティア養成講座「高齢社会にボランティアは何ができるか」
第1回 5/17(土) 東京教区補佐司教 アンドレア・レンボ師 高齢社会におけるボランティア
第2回 5/24(土) 精神科医 石丸昌彦氏 高齢者の心と身体
第3回 5/31(土) 緩和ケア医 五味一英氏 最後まで自宅での希望に応える
第4回 6/14(土) 生命科学者 中村桂子氏 高齢期を心豊かに
第5回 6/28(土) 社会福祉士 峰毅氏 高齢者を支える社会の仕組み
福島の地からカリタス南相馬 第40回
第12回いのちの光 3・15フクシマ 「フクシマが背負ってきたもの伝えつづけるもの」
「いのちの光3・15フクシマ」実行委員
畠中千秋(聖心会)
 中筋純館長のお話
中筋純館長のお話
「2011年3月15日」それは、東日本大震災により東京電力福島第一原子力発電所が3度目の爆発を起こし、放射性物質が福島県を中心とした広い範囲に拡散した日です。
今年3月15日、カトリック原町教会での現地報告では、「アートを通じて伝える原発事故」と題して、写真家で「おれたちの伝承館」館長の中筋純氏のお話を拝聴しました。その後、幸田和生東京教区名誉補佐司教司式のミサが行われました。翌16日、仙台・元寺小路教会では、「内部被爆の治療をライフワークとする医師が語る被爆の健康被害の真実」と題して、北海道がんセンター名誉院長の西尾正道氏の講演をいただきました。
南相馬市小高区にある「おれたちの伝承館」を訪れ、展示作品を見て、アートは言葉以上の存在で、心に直接響く力を持っていると実感しました。東京在住の中筋氏の「コンセントの向こう側にあるものを想像してみる」という言葉が強く印象に残っています。
ミサの中での幸田和生司教のお話も現実の上に立って語られた言葉として心に響きました。2011年の原発事故後、原町教会の隣にあるさゆり幼稚園には閉園の危機がありました。放射能を被った土地で幼稚園を再開すべきではないという強い意見があったからです。しかし、幼稚園を必要としている家族もいました。幼稚園の先生たちは園庭を除染し、幼稚園を再開し、園児を受け入れました。放射能の問題では、どこまでが安全でどこからが危険かという問題は難しく、これからも続くことでしょう。
この現実の中で私たちは何を選んで何を捨てて暮らしていくのでしょうか?たくさんの労力と人々の悲しみ・犠牲の上につくられた「電気」を、これから先どのようにつくり出し、どのように使っていくのか?いつ完了するかわからない、原発事故後の処理も含めて、フクシマの課題は福島だけの課題ではなく、日本中の課題であり、世界の課題でもあるとあらためて思います。
カリタス東京通信 第22回
東京同宗連第44回現地研修会に参加して
部落差別人権委員会東京教区担当者
枝松 緑
1月29・30日、水平社発祥の地である奈良県にて東京同宗連(「同和問題」にとりくむ宗教教団東京地区連帯会議)の現地研修会が開催され、加盟10教団から23人が参加した。
1日目に訪問した水平社博物館では、水平社が創立され「水平社宣言」が生まれた背景などについて文献や写真が展示されていた。橿原(現・御所市柏原)の数人の青年たちは、ある論文に大きな衝撃を受け、西光寺門前近くに「水平社創立事務所」を掲げた。組織名の「水平社」は「絶対に差のできないものは『水平』である」から名付けられている。1922年2月には水平社創立趣意書「よき日の為に」を発行、1922年3月に全国水平社創立大会が開催され、その場で採択されたのが「水平社宣言」である。柏原では、環境・風景・街の佇まいなど彼ら青年たちの育ちの体験を感じ、また、当時の思想哲学的に思索材料・文献・人的交流に恵まれたと思われる「人権のふるさと公園」も訪れた。博物館玄関前方に本馬山(ほほまのおか)、間に満願川が流れ、小橋を渡り、西光寺、阪本生家跡、駒井宅跡地、東に中方川、曽我川があり、当時皮革産業地域として栄えていた土地である。彼らは、一族、親、自らが産まれながらに受け、置かれ、扱われたことを自分たちの言葉で表し、宣言した。
2日目は、おおくぼまちづくり館を訪れ、天皇制による「洞(ほうら)部落強制移転」について学んだ。江戸封建制から公武合体、大政奉還、明治維新へと突き進む中、神武天皇陵の拡張を画策中であった政府宮内省により洞部落の人たちが強制移転となった。洞村には約0.13平方キロの面積に208戸1054人が住み、約半数は土地・家を持たない人たちだった。村の根本的改善を考えた洞村の人たちは、洞村移転を促す民間の動きもあり、土地全部を宮内省に献納、堂々たる条件付きの「同意書」を残している。交渉の過程では、移転先の土地から外へ出てはいけないとされる居住制限は「土地家屋を所有すとも、一切居住しえざるごときは、居住の自由を保障せられたる憲法より受くる臣民の特権を剥奪せらるるものなり」との意見書も残されている。当時から相手と対等平らな関係性を保ち、人権意識が高く、目覚めていた方々だったと感じ入った。神武天皇陵前から山側へ分け入り登ること約一時間にある旧洞部落跡地を歩いた。現在は木々に覆われた山地、人の生活を感じさせるものが少ないなか、石積みで囲われ水を湛えた井戸が残っていた。なぜかホッと安堵。しばしそこで生活した方々を想った。
天皇制と部落差別の関係を神武天皇陵と洞部落が象徴している。「部落完全解放『よき日の為に』の『よき日』を迎えるまで語り継ぎたい」との案内人の想いを受け止めつつ現地研修会を終了した。
編集後記
イエスが背負った十字架は
誰かの十字架ではなく、この私の十字架だ
ゴルゴダへの道は
誰かではなく、この私が歩くはずだった道だ
十字架のイエスのまなざしは
この私への愛のまなざしだ
十字架の道行きは
イエスから私への
イエスと私との
究極の愛の道行きだ(Y)