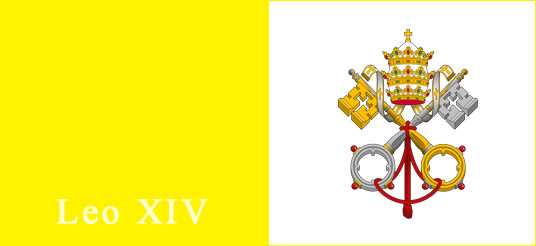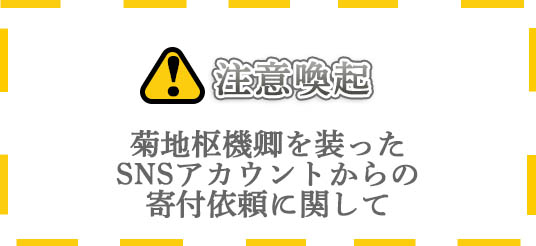教区の歴史

<これからの教会を考えよう> 「タイタカトリック」
2001年07月14日
小宇佐 敬二 (東京教区司祭)
2001年7月14日
(1)
船は順調に航行しているように思われた。彼は、新天地に向かい、波を蹴立てていく船の舳に立つのが好きだった。頬をうつ風は、あたかも新天地から吹いてくるようで、未来への夢を膨らませてくれる。水平線の彼方にまだ見ぬ新天地を思い描きながら、いつものように目をつぶり、その風を思い切り吸い込むのである。そして、しばらく風を全身で味わう。髪をかき乱し、耳に響く音。衣服のあちこちが打ち震え、その振動は心地よく全身を駆け巡る。新天地への夢は彼の体から溢れんばかりに充満し、今、ここに立っていることの喜びに酔いしれるのである。
彼の中に、何か違和感が走った。ビクンと腹の底を突く違和感、こんなことは初めてである。彼ははっと目を見開き、辺りを見回した。そして、水平線に向かって目を凝らした。「何かが違う。」腹の底の違和感を、明晰な意識の上に立ち上らせ、海を見た。「海の色が違う。」「この船は新天地に向かっていない。」彼の背筋に戦慄が走り、全身に鳥肌の立つ思いがした。彼は急いでデッキを駆け戻り、船長を探した。
「船長、船長。」彼は船長室に駆け着くと、激しくドアを叩き、船長を呼んだ。
「どうぞ。」緒方船長の重々しい声が聞こえた。彼は勢い良くドアを開けると、息をきらしながら言った。
「船の、船の向きが違っていませんか、この船は新天地に向かっていないのでは。」
「わたしも気が付いています。今、くわしく調べさせているところです。」机の向こう側の椅子に、深く腰をおろして、沈痛な面持ちで緒方船長は答えた。船の航行の様子を詳しく調べさせ、いまそのデーターが届くのを待っていたようである。
そこへ、測量計測室の永川室長が急ぎ足で入ってきた。そして、緒方船長に資料を手渡しながら言った。
「確かにこの船はコースを外れています。直進しているように見えますが、実は大きく右に弧を描きながら、今、ほとんど北北西へ向かっています。このままでは、あと6時間ほどで氷海に突っ込んでしまいます。」
「やはり。」緒方船長の沈痛な面持ちは、悲痛に歪んだ。
船が氷海に入る。それは極めて危険なことである。そこには無数の氷山が浮かび、北に進むにつれ、その数は増し、やがては、大陸のように張り詰めた氷原にぶつかる。その氷原に至るまでもなく、船は氷山を避けきれず、衝突し沈没してしまうだろう。 彼は、6時間と聞いて半ば安堵した。同時に、緒方の悲痛な面持ちが理解できなかった。
「船長、操舵室にいきましょう。左に舵を取れば、コースを取り戻せるでしょう。」彼は、不可解な思いに駆られながら、緒方に言った。
船長は立ち上がり、重い足取りで操舵室に向かった。彼は緒方の後に従ったが、その重い足取りに不可解さは拭いきれない。
「この船に、操舵室はあるのだが、その舵は効かないのだよ。」緒方船長はつぶやいた。
「どうしてですか」彼は驚いてたずねた。
「この船には舵がない。そう、巨大な箱舟なんだ。いや、この船に乗っている人、全員の意思が、この船の向きを決める舵になる。動力も同じ‥。」
操舵室に入ると、緒方はあきらめの気持ちを確かめるように、操舵器を回した。何の抵抗もなく、何の反応もなく、操舵器はからからと回りつづけている。
緒方船長は操舵室を出ると、艫に向かって歩き始めた。彼もそれに従った。緒方は一言も口を開かないまま船の艫に立った。あたかも航跡を確かめるように水平線を見つめている。航跡は真っ直ぐのびているように見えるが、心なしか左に弧を描いているようにも見える。
「船長室にもどろう。何か方策があるはずだ。」緒方船長はゆっくりと歩き出した。悲壮な決意がその面持ちに浮かんだ。
緒方がこの船、タイタカトリックの船長になったのは数ヶ月前からである。それまで船長だった白八木は体調の不良を訴え引退した。舵も機関もままならないこの船を操るのに疲れたのかも知れない。
緒方は船長室に入ると、また、深く腰をおろした。
そこへ、先の一等航海士毛利が駆け込んできた。毛利は白八木船長のもとで長年一等航海士を勤めてきたが、白八木船長とともにその責任を辞し、今、この船の構造的な欠陥を調査している。
「原因が分かりました。乗客が右舷に片寄って乗り込んでいたようです。それで船のバランスがずれたのかと思われます。バラストを移動したぐらいでは、進路を取り戻すことはできないでしょう。乗客全員が甲板に上がり、全員が左舷に寄れば、船を左に回すことができるかとは思いますが」毛利は一筋の望みを船長に進言した。
「とにかく、乗員、乗客全員に、今の危機的情況をアナウンスしましょう。乗客の協力なしにはこの危機を脱することはできないのですから。」毛利とともに船長室に来ていた胡田航海士が叫んだ。
(2)
この船の船内は九つの居住区に分けられている。さらにその居住区は九つほどの区画に分けられ、それぞれの区画で乗客は乗務員のサービスを受けていることになっている。
かねてから緒方は乗客に対するサービスが行き届いているのか、気がかりであった。長い航海生活の中で、日常が惰性に流されているようにも感じている。乗員も乗客も航海の目的地である新天地を意識しているのか、そこでの生活に夢や期待を持っているのか、それが伝わって来ない。意思の疎通がこの船の舵取りになるはずなのだが、舵取りが思うにまかせないのは、どうも疎通という風通しがはなはだ滞っているように感じているのである。
「アナウンスすると言っても、どうすればこの情況を乗員乗客全員に伝えられるのだ。」
陰鬱な表情で緒方はつぶやくように言った。
「まず、わたしたちが手分けして、各居住区を回り、呼びかけます。何はともあれ、動き始めなければ、何もできません。」
胡田は皆をうながすように言った。
「そして、何人でもいい、1時間後に大ホールに集まってもらいましょう。」
「そう、それしかない。今、10時過ぎか。」
緒方は腕時計を一瞥して、号令をかけた。
「1時間後、午前11時に大ホールで集会を行います。そこでわれわれが陥っている情況を詳しく説明し、乗員乗客の協力をお願いしましょう。皆さんは手分けして、一人でも多くの人に集まってもらって下さい。」
彼も緒方船長の依頼を受けて、乗員乗客に事の情況を伝えることになり、階下の居住区へ降りていった。途中、この船の大ホール、パーティーや集会、懇親会などを行う数百人収容できる大ホールの脇を降っていったのだが、その大ホールが閑散としていて、ながいこと使われていないようなさまに、違和感を覚え。「この船はどうなっているのだろう。」不可解な思いをつのらせながら、彼は居住区へ降りていった。
階段を降りた正面に、この居住区を統括する事務室があるはずである。そこにフロントのカウンターがあるのだが、カウンターには誰も立っていない。カウンターの隅に置いてある呼び鈴を叩いてみた。チーンチーンと澄んだ音が響く。2度3度と叩いてみた。しかし、事務室からは誰も出てこない。彼は待ち切れなくなって、カウンター脇の蝶開きのドアから中に入り、事務室のドアを開けた。事務室には誰もいない。彼には即座には事態が呑み込めなかった。カウンターから出ると、どうしたものかととまどってしまった。
と、すぐ先の通路から客室係りの制服を着た乗務員があらわれた。
「そこには、誰もいませんよ。」
「でも、ここはこの居住区全体を統括しスムーズなサービスを行うための事務室でしょう。」
「この居住区は統括などされていません。みんなそれぞれ勝手にやってますからね。サービス係は乗客に頼まれたことを、適当にこなしていけばいいんですよ。」
「今、この船が大変なんです。進路をはずして、すぐにでも氷海に入ってしまう。この船は新天地には向かっていないんです。」
「船の進路のことは、上の人にまかせておけばだじょうぶです。何分わたしは今、5017号室のお客さんに、氷と水を持ってくるように頼まれまして、それに、5081号室には毛布を持っていかなければいけません。これだけのお客では客室係は手不足です。けっこう忙しいんですよ。」
客室係りの乗務員は、足早に去って行った。その向こうには厨房でもあるのだろう。
「11時にホールに来てください。船長から説明があります。」
彼は、乗客係りの後姿に呼びかけた。
「こんな非常事態なのに、氷と水でもあるまい。」彼の胸にやりきれない憤りが沸沸と湧き始めてきた。通路を右に入るとすぐ5017号室があった。彼は勢い良くドアをノックした。
「どうぞ。」
おっとりした声が答えた。
彼が中に入ると、数組のグループがテーブルを囲んでカードに興じている。酒を飲みながら、たばこをくゆらしながら、談笑しながら。見るからに穏やかな風情である。
「皆さん、今、カードどころではありません。この船は進路をはずして、今にも氷海に突っ込んでしまいそうなのです。この船は新天地に向かっていないのです。」
彼は必死の面持ちで訴えた。
「新天地に向かっていないだって。」
「はい、船は大きく進路をはずして、北北西に向かっています。」
客の一人が答えた。
「でも、そのことはわれわれにとってはどうでもいいことだ。われわれはのんびりとこのクルージングを楽しんでいる。どこに向かうかはさほど関心がない。」
「でもこのまま行けば、氷海に入り、」
彼の言葉を遮って、別の一人が言った。
「氷海のクルーズもまた乙なもんじゃないか。それに、この船が沈む訳がない。何年もこうやって走りつづけてきた。」
(これじゃ話にならない。こんな所で時間をつぶせない)彼はあせりともいらだちとも言えない気持ちにかられて、尋ねた。
「お隣りの方は何をなさっていますか。この事を皆に伝えなければならないのです。」
「隣りの人、良く知らないな、あまり関心がないもんで。それより、どうだい。一緒に楽しもう。船旅はのんびり楽しむのが一番だ。」
「わたしはこの事を皆に知らせなければなりません。それより11時に大ホールに来て下さい。船長から説明があります。」
彼はそそくさと5017号室のドアを閉めると、すぐ隣りの5018号室のドアを叩いた。
「どうぞ。」
優しげな女性の声が応えた。
豪華な色調で整えられたインテリア、テーブルには簡素にアレンジされた花が飾り付けてある。そのテーブルを囲んで、数人の初老の女性たちがお茶を飲んでいる。淡い紅茶の香りが、ほのかに漂ってくる。
「あら、よくいらっしゃいました。わたしたちは今、『新天地の夢』について分かち合っておりましたの。どうぞ、お仲間にお入り下さいませ、おいしいケーキもございましてよ。」
「それどころではないのです。今、この船は新天地には向かっていません。まもなく氷海に入り、とても危険な状態なのです」
彼のことばを遮るように、婦人は言った。
「危険だなんて、そんなことはありません。わたしたちはいつも、この船の安全のためにお祈りしていますもの。神様がいつもお守りくださっています。」
「それに、新しい船長の緒方さん、この前ちょっとお顔を拝見しましたの。とってもステキな方で、優秀なお方でいらっしゃいましてよ。もちろん、先の白八木船長もステキでございましたけど。あの方におまかせしていれば大丈夫ですよ。」
「その緒方船長が11時に大ホールに集まるように申しております。船長から詳しく説明があるはずです。ぜひ、いらして下さい。」
「はいはい、わたしどもはいつもお祈り申し上げています。それより、どうですか、お茶をめしあがって、新天地の夢をお話しくださいましな。」
「だから、それどころではないのです。このままだと船は沈んでしまうのです。そのことを皆に伝えなければなりません。」
「まあ、それは大変ですね。そのようなことにならないように、お祈りしてます。」
部屋を出た彼は、焦燥にかられる思いがした。