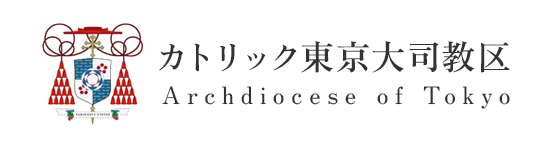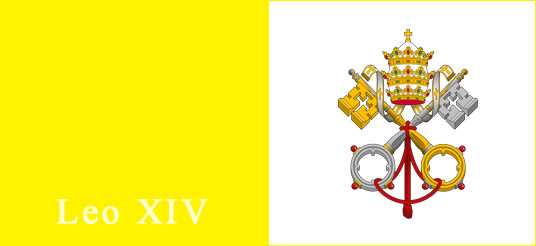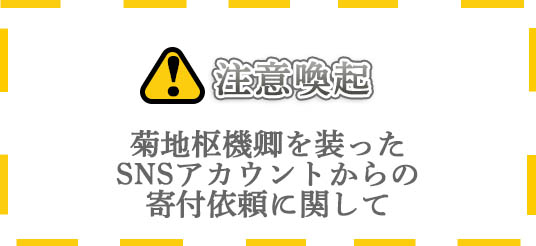大司教

週刊大司教第二百二十九回:年間第三十主日
2025年10月27日

時間は瞬く間に過ぎ去り、10月も最後の日曜日とないました。今月の最初の頃は枢機卿名義教会着座式のためにローマにいたことが、遙か昔のようです。写真は10月8日の一般謁見です。
先週10月19日は、世界宣教の日でありました。中央協議会のホームページに以下の説明が掲載されています。
「世界宣教の日」は、すべての人に宣教の心を呼び起こさせること、世界の福音化のために、霊的物的援助をはじめ宣教者たちの交流を各国の教会間で推進することを目的としています。この日の献金は、各国からローマ教皇庁に集められ、世界中の宣教地に援助金として送られます。日本の教会は、いまだに海外から多くの援助を受けていますが、経済的に恵まれない国々の宣教活動をさらに支援できるように成長していきたいものです。
教皇庁宣教事業に関しては、日本における対応部署のホームページが設けられており、そこに詳細が記されていますので、一度お訪ねください。現在の日本全体の教皇庁宣教事業担当者は、東京教区の門間直輝神父様です。
本日の週刊大司教でも触れた今年の世界宣教の日の教皇メッセージは、そのサイトに掲載されています。こちらからご覧ください。

以下、本日午後6時配信、週刊大司教第229回、年間第三十主日のメッセージです。
年間第30主日
週刊大司教第229回
2025年10月26日前晩
わたしたちの目は、節穴です。肝心な本質が見えていません。往々にして、思い込みと勘違いを引き起こしています。ルカ福音は、本質を知るためにどこに目を向けるのかを記しています。
福音は、「神様、罪人のわたしを憐れんでください」と、目を上げることもなく胸を打った徴税人ほうが、自らの正しい行いを誇るファリサイ派の人よりも、神の目には正しい人とされた話を記します。当時の徴税人は様々な不正に手を染めていたとも言われ、多くの人の目には正しい人とは映らなかったことでしょうし、ファリサイ派の人は掟を忠実に守っていることから、多くの人からは正しい人と見なされていたことでしょう。神の目には本質が見え、わたしたちの目は節穴です。
ファリサイ派の人が自分を見つめています。自分しか見えていません。わたしはどういう人間なのか。彼が語るのは、自分のことばかりであり、すなわち彼は自分の世界に閉じこもっているので、その世界では自分が一番に決まっています。ですから臆面もなく報いを求めます。
それに対して徴税人は、その目を神に向けています。自分がどういう人間であるのかと言う判断をするのではなく、それをすべて神の判断に委ねています。つまり二人の違いは、自らの存在を神に委ねているのか、委ねていないのかにあります。
わたしたちには、単にマナーとして謙遜になることが求められているのではありません。求められている謙遜さは、神にすべてを委ねているのかどうかであります。御旨に従うことは、格好良く見栄え良く生きることではありません。
自分の名誉のためではなく、神が救いたいと望んでおられるすべてのいのちに福音が届けられるように、神の計画に身を委ね、すべてを尽くして福音をあかしするものとなりたいと思います。
先週、10月19日は世界宣教の日でありました。教皇レオ14世はこの日のためのメッセージのテーマを「諸民族の中で生きる希望の宣教者」とされ、「キリストの足跡に従って希望の使者となり、それを築く者となるという根本的な召命」がキリスト者ひとり一人と教会共同体にはあるのだと強調されています。
その上で教皇は、第二バチカン公会議の現代世界憲章に記されている、「「現代の人々の喜びと希望、苦悩と不安、とくに貧しい人々とすべての苦しんでいる人々のものは、キリストの弟子たちの喜びと希望、苦悩と不安でもある。真に人間的なことがらで、キリストの弟子たちの心に響かないものは何もない」(『現代世界憲章』1)を引用して、「キリストの弟子たちはまず、自らが希望の「職人」となり、混乱し不幸に陥りがちな人類を回復させる者となる修練を積むよう求められています」と、すべてのキリスト者がそれぞれの立場に応じて福音宣教をする者となるように求めておられます。
わたしたちも自らの宣教者としての使命を思い起こし、福音をよりふさわしくあかしする道を探り続けたいと思います。