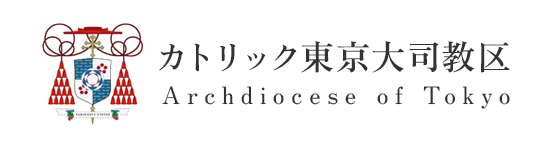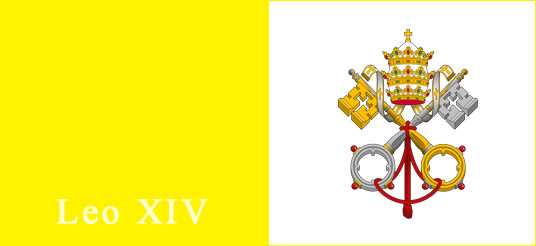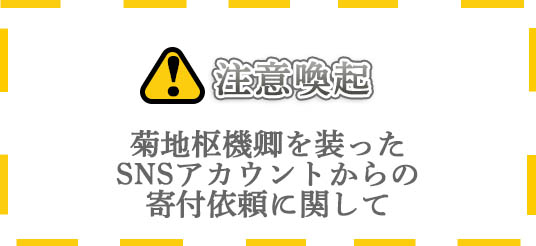大司教

週刊大司教第二百二十六回:年間第二十六主日
2025年09月29日

9月最後の日曜日となりました。年間第26主日にあたるこの日、9月最後の主日を、教会は世界難民移住移動者の日と定めています。
この日にあたっての教皇レオ十四世のメッセージは、「移住者-希望の宣教者」をテーマとしています。こちらのリンクから全文をお読みいただけます。メッセージの中で教皇レオ十四世は、次のように指摘しています。
「多くの移住者、難民、避難民は、彼らが神に身をゆだね、未来のために逆境に耐えることを通して、日々の生活の中で生きる希望の特別な証人となっています。彼らはこの未来の中に、幸福と総合的な人間的発展が近づくのを垣間見るからです。彼らにおいてイスラエルの民の旅の経験が繰り返されます」
教皇様は、教会は神の民として旅を続ける存在であることを、難民や移住者の存在によって思い起こさせられており、教会が歩みを止めてある一点にとどまるときに神ではなく世に属する者となるとして、次のように記します。
「移住者と難民は教会に、自らの巡礼者としての側面を思い起こさせてくれます。教会は、対神徳である希望に支えられながら、最終的な祖国に到達することを目指してたえず歩み続けるからです。教会は、「定住」の誘惑に屈し、「旅する国」(civitas peregrina)――天の祖国を目指して旅する神の民(アウグスティヌス『神の国』[De civitate Dei, Libro XIV-XVI]参照)――であることをやめるとき、「世にある」者であることをやめ、「世に属する」者となるのです」
こう述べた後で、教皇様は、信徒として移住する人たちや難民の方々の存在に焦点を当て、彼らが福音を告げる宣教者であるとして、次のように記しています。
「とくにカトリック信者の移住者と難民は、彼らを受け入れる国において、現代の希望の宣教者となることができます。彼らは、イエス・キリストのメッセージがまだ届いていないところに新たな信仰の歩みをもたらし、日常生活と共通の価値の探求による諸宗教対話を始めることができるからです」
国連難民高等弁務官事務所によれば、現在四千万人を超える人が国境を越えて難民となり、さらには七千万人の人が自国内での避難民となっています。国連によれば、この数は10年前と比較しても倍増していると言います。
現時点で国際カリタスは、それぞれの国のカリタスを通じて、カトリック教会として難民の方々の支援や救援を行っています。もちろん現時点ではウクライナやガザの状況は困難を極め、とりわけガザでは虐殺とも言うべき状況が継続しています。神から賜物として与えられたこのいのちの尊厳が損なわれる状況を、教会は見過ごすことはできません。国際カリタスは聖座と共に、あらゆるチャンネルを通じて、停戦の実現と人道支援の強化を求め続けています。
以下、27日午後6時配信、週刊大司教第226回、年間第26主日のメッセージです。
年間第26主日
週刊大司教第226回
2025年9月28日前晩
10年前にエコロジカルな回心を問う「ラーダート・シ」を発表された教皇フランシスコは、その中で、「現在の世界情勢は、不安定や危機感を与え、それが集団的利己主義の温床となります(205)」と指摘されていました。10年が経過して、その状況は全く改善していません。
教会は9月最後の主日を、世界難民移住移動者の日と定めています。この日にあたり教皇レオ十四世は、「移住者――希望の宣教者」と題したメッセージを発表されています。
その中で教皇は、「現代の世界情勢は、残念ながら、戦争と暴力と不正と異常気象によって特徴づけられています。そのため何百万もの人々が故郷を離れ別の土地に避難することを余儀なくされています」と現状を指摘し、世にはびこる利己主義的価値観を踏まえて、「限られた共同体の利潤のみを求める一般的な傾向は、責任の共有、多国間の協力、共通善の実現、人類家族全体のための国際的な連帯に対して深刻な脅威となっています」と指摘しています。
ルカ福音が記す金持ちとラザロの話には、まさしく世界が自分を中心にして回っているかのように考え振る舞う金持ちの姿が描かれています。利己主義に捕らえられた心には、助けを求めている人は存在する場所すらありません。自分の利益しか眼中にない生き方の姿勢を捨てることができないからです。死後の苦しみの中で神の裁きに直面するときでさえ、金持ちの心は自分のことしか考えず、それを象徴するように、この期におよんでもラザロを自分の目的のために利用しようとします。
教皇フランシスコは、わたしたちがこころの扉を開いて、出向いていく教会であることが、集団的利己主義から脱却する道であることを繰り返し指摘し、そのためにこそ、教会はシノドスの道を歩みながら、互いに支え合い、隣人の叫びに耳を傾け、祈り合いながら、神に向かって歩み続けることこそが不可欠であることを強調されました。
希望の巡礼者として聖年の歩みを続けているわたしたちに、教皇レオ十四世は、先ほどのメッセージの中で次のような指摘をされて、移住者と難民こそがそのような社会のただ中で、希望の宣教者となるのだと指摘しています。
教皇は、「カトリック信者の移住者と難民は、彼らを受け入れる国において、現代の希望の宣教者となることができます。彼らは、イエス・キリストのメッセージがまだ届いていないところに新たな信仰の歩みをもたらし、日常生活と共通の価値の探求による諸宗教対話を始めることができるからです。実際、彼らは、その霊的な熱意と活力によって、硬直化し、不活発になった教会共同体を活性化することに貢献できます」と述べています。
わたしたちはこの現代社会の中で、希望を掲げながら旅を続ける宣教者です。FABC50周年の文書には、「宣教は、教皇フランシスコが「自己中心の姿勢」と呼ぶものへと向かうわたしたちの傾向の対極にあるものです。自己中心的になるのは、わたしたちは自分自身のために存在するのではなく、むしろ世界のために存在するのだということを忘れてしまうときです」という指摘があります。
わたしたちがこころの扉を開いて、出向いていく教会であり続けることができるように、イエスの呼びかけに耳を傾けて歩み続けましょう。