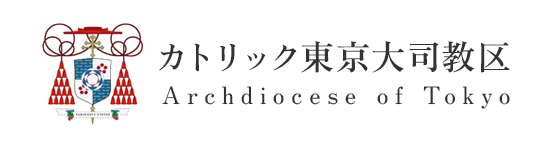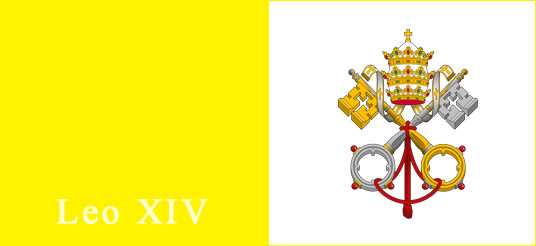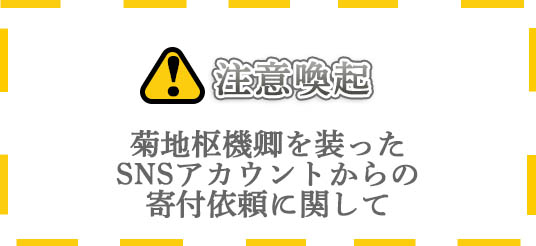大司教

週刊大司教第二百二十五回:年間第二十五主日
2025年09月24日
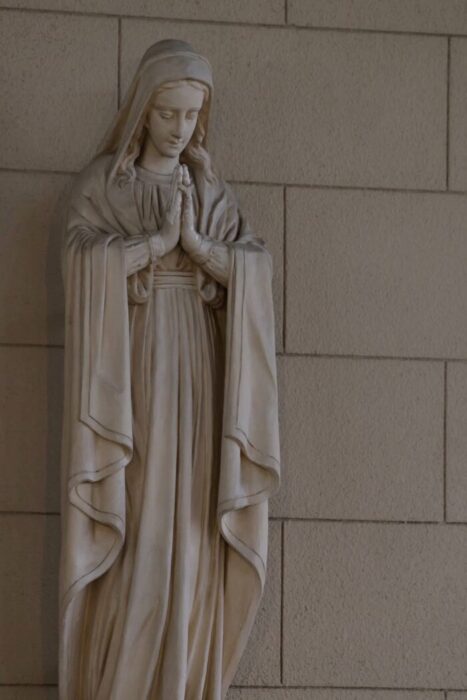
9月も半ばを過ぎ、暑さの続いた東京も少し秋の気配を感じるようになってきました。9月21日は、年間第25主日です。
2004年9月20日、いまから21年前に、新潟において司教叙階を受け、新潟教区司教となりました。その日は、岡田大司教様が主式の司教叙階式でした(下の写真)。この21年の間、2004年から2017年までは新潟で、またその間、2009年から2013年までは札幌を兼任し、そして2017年末からは岡田大司教様から引き継いで、東京教区の大司教を務めさせていただいております。この間、多くの方々のお祈りと励ましをいただき、務めをなんとか果たすことができてきました。

教区司教としての務め、またカリタスやアジア司教協議会などの務め、日本の司教協議会での務めなどなど、様々な務めを果たしていく中で、多くの方の助けと協力をいただいてきたことに感謝いたします。皆さん、本当にありがとうございます。
まだこれから数年はこの務めを続けていくことになるだろうと想定しています。もっとも、すべては神様の計画ですからどうなるのかは分かりませんけれど、これからも与えられた場で求められる務めをふさわしく果たしていくことができるように、みなさまの助けと協力とお祈りをお願い申し上げます。これからも、どうぞよろしくお願い致します。
これまでも繰り返し説教などの機会に触れてきましたが、聖地の状況はますます混迷を深めています。歴史的な背景から生み出される課題の政治的な解決は一朝一夕では得られないのは、聖地をはじめとする中東地域の複雑な現実ですが、教会の立場からは政治的意図の違いを超えて、まず第一に神から与えられた賜物であるいのちを、すべからく守ることを基本として、声を上げ続けます。いのちは例外なくすべてが、その始まりから終わりまで護られ、神から与えられた人間の尊厳が尊重されなくてはなりません。

わたしが現在責任者と務める国際カリタスは、世界で活動する他の44の国際NGOなどと共に、9月12日に短い声明を発表しました。原文はこちらの国際カリタスのサイトで英語でご覧ください。以下、仮の機械翻訳を掲載します。
イスラエル軍によるガザ市への攻撃が激化し、全市民に対する強制移動命令が出されている中、家族は避けがたいジレンマに直面しています。逃げれば道中や人であふれかえっている避難所での死の危険があり、留まれば隠れているシェルターへの容赦ない爆撃に直面します。どちらにしても、飢餓と包囲が待ち受けています。
「私たちの唯一の要求は命です。私たちはあなたと同じ人間です。私たちは尊厳と安全の中で生きたいのです。飢えや爆弾で死にたくはありません。」
アイマン(仮名)、ガザ市で家族と避難している父親100万人近くのパレスチナ人が、飢え、悲しみ、そして何度も移動を強いられながらガザ市に残っています。イスラエルの作戦が続けば、病院は孤立し攻撃され、避難所や学校は爆撃され、逃げることができないほど弱い、年老いた、または病気の人々には、死しか残されていません。
「私たちは一つの場所から別の場所へ逃げることに疲れました。」
アビール(仮名)、人道支援活動家同時に、イスラエルは人道的な活動を故意に妨害しています。援助トラックは引き続き拒否され、国際NGOは不透明な登録制度によって宙ぶらりんの状態に置かれ、飢饉が深刻化しています。
国際司法裁判所は、ガザのパレスチナ人がジェノサイドから保護される権利を持っていることを認めています。各強制移動の行為や飢餓の高まりは、その危険性をより確実なものにしています。そして、世界はこれが起こるのを見て見ぬふりをすることはできません。
私たちの物資を通過させてください。私たちに働かせてください。この攻撃を止めてください。
以下、20日午後6時配信の、週刊大司教第225回、年間第25主日のメッセージで原稿です。なお文中に登場するFABCは、アジアの各国地域にある司教協議会の連名組織で、事務局を現在はバンコクに置いています(以前は香港にありました)。現在の会長はインドのゴアのフィリッポ・ネリ・フェラオ枢機卿、副会長がフィリピンのパブロ・ダビド枢機卿、事務局長をわたしが務めています。英語ですがホームページがありますので、ご参照ください。
年間第25主日
週刊大司教第225回
2025年9月21日前晩
ルカ福音は、「ごく小さな事に忠実な者は、大きな事にも忠実である」というイエスの言葉を記します。
わたしたちはどうしても、すべてに対して全身全霊を傾けるよりは、そこから自分の得られる利益を勘案して物事の価値を計り、ある意味選択をしながら行動してしまいがちです。どのような選択をするのかに、わたしたちひとり一人の価値観が反映されます。その時々の事情に応じて、わたしたちは、いわば、「神と富」のどちらか必要な方を選択することを繰り返しています。それに対してイエスは、どちらかをはっきりと選択し、選択したのであれば小さなことにも大きなことにも、全身全霊をかけて忠実であれと命じています。
わたしたちが選択する道は、神の愛といつくしみから、誰ひとり忘れ去られることなく、また誰ひとり排除されることのない世界を実現する道です。神の愛はすべての人に向けられているにもかかわらず、その愛の実現を妨害しようとするのは、わたしたちの不忠実さであります。わたしたちは神の愛といつくしみの実現の前に立ちはだかる様々な障壁を取り除くという大きな目的を達成するために、目の前の小さな事への取り組みを忠実に果たしていかなくてはなりません。
アジア司教協議会連盟(FABC)は、2022年10月に開催された創立50周年の総会で最終文書「アジアの諸民族としてともに旅する」を採択しました。その冒頭で、これからの歩みの中心にあるのはシノドス的な教会の道であることを明確に記し、「シノドス的な教会には、交わり、参加、宣教という、不可欠な3要素が」あることを指摘します。
その上で、「交わり」の重要性について、「排他性の傾きに対するアンチテーゼです。洗礼を受けた人は皆、尊厳において平等です。・・・教会には、一流の人も二流の人もありません。霊はさらに、わたしたちが同じカトリック信者とだけでなく、すべてのキリスト者、人類すべて、造られたものすべてとの交わりを結ぶよう、力を与えてくれます。・・・霊との交わりのうちにおいてのみ、わたしたちは弟子の共同体へと成長し、パン生地の塊の中のパン種のように働く、キリスト教基礎共同体、人間基礎共同体の建設者となることができるのです」と指摘しています。
さらにFABCは2025年3月15日に司牧書簡を発表し、「交わり」を具体的に生きるために、特にエコロジーの側面に取り組むことの重要性を指摘しました。その上で同書簡は、9月1日から10月4日まで、ちょうどいま祝われている「被造物の季節」にあって、エコロジカルな回心を交わりのうちに具体化するよう、次のような取り組みを呼びかけています。
第一に、「エコロジカルな責任についてわたしたちの共同体の学びを導く」こと。次に、「より簡素で、より持続可能なライフスタイルを奨励する」こと。そして、「神・人類・宇宙とのわたしたちのかかわりを深める、創造の霊性を培う」ことであります。
シノドスの道の歩みはエコロジカルな回心の道と密接に関わり、それは別々の事柄ではありません。シノドスの道の歩みを深めることは、教会で交わりを持つわたしたちの生き方そのものを見直すことにも繋がります。そのためにも、この数年の間に発表されてきたシノドスの文書などをしっかりと学ぶ時を持ち続けたいと思います。シノドスは過去のことではなく、いまわたしたちが歩む道であり、そのためにも小さなことにも忠実であるものでありたいと思います。