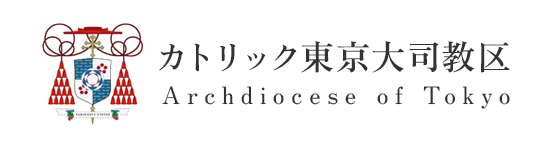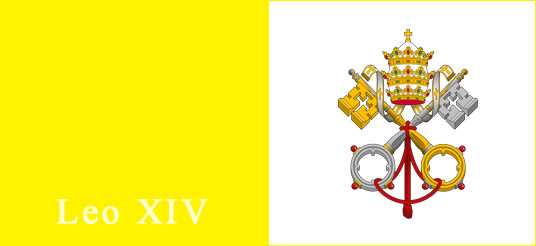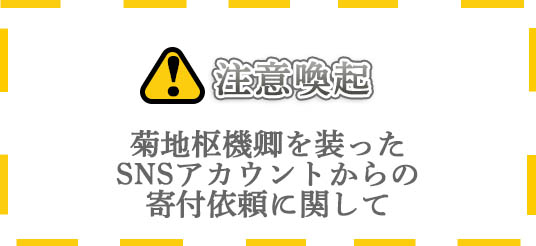大司教

週刊大司教第二百二十三回:年間第二十三主日
2025年09月09日
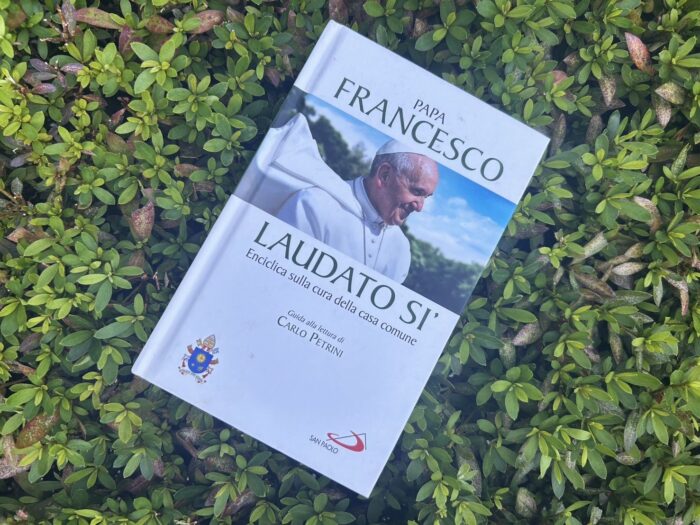
あっという間に9月になりました。9月7日は年間第23主日です。日本の教会では9月の第一主日が被造物を大切にする世界祈願日です。教皇様のメッセージはこちらのリンクです。
先週の週刊大司教第222回の記事でも触れましたが、9月1日に始まって、アシジの聖フランシスコの祝日である10月4日まで、日本の教会は「すべてのいのちを守る月間」と定めています。これは219年に、「すべてのいのちを守るため」をテーマと掲げて教皇フランシスコが日本を訪問されたことを記念し記憶するために日本の教会が定めました。また世界の教会は、エキュメニカルなコンテキストの中で、この同じ期間を「被造物の季節」と定めています。今年は特に、2015年に教皇フランシスコが「ラウダート・シ」を発表されてから10年ですので、節目を祝うイベントが多く予定されています。
司教協議会は、先般、「ラウダート・シ」をテーマとして様々な啓発活動を行う担当を、「デスク」から「部門」へ変更しました。これはこれまで別の委員会に分かれて活動していた諸課題を、福音宣教司教委員会と社会司教委員会に大きく分け、その中でテーマに分かれて委員会や部門を設置して行くことになった組織変更に伴っています。
この二つの司教委員会の他の大きな分類は、常任司教委員会と広報宣教司教委員会で、さらにカリタスジャパンが事業体として委員会組織から離れました。現在の司教協議会の委員会の構成は、こちらのリンク先をご覧ください。なおこれらの委員会組織は司教協議会の枠組みの中にあり、司教を中心として動きます。その具体的な事業活動の事務局がカトリック中央協議会で、こちらは事務局長をトップに、具体的な作業を行う組織です。なお中央協議会で働く司祭は、全国の三つの教会管区からそれぞれひとりずつ派遣されている司祭の合計3名だけです。
「ラウダート・シ」をテーマとする部門もデスクから福音宣教司教委員会内の部門になったことで、さらに宣教司牧的側面から啓発活動を強めていくことが期待されていますし、その意味で、現在行われている「すべてのいのちを守る月間」の方向性を明確にしてくださるものと期待しています。

なお9月4日(木)に、日本のシノドス特別チームは大阪は玉造の大阪教区本部を会場に、全国の司教様方と、各教区のシノドス担当者、合計47名を集め、今回のシノドス性のシノドスにそのはじめから深く関わり、教皇フランシスコと緊密にやり取りをしていたオロリッシュ枢機卿様を講師に迎え、一日の研修を行いました。

他の国でもバチカンのシノドス事務局のグレック枢機卿様やシスターナタリーを迎えて研修会をしていますが、どうしても言葉の壁があるため、今回、オロリッシュ枢機卿様に日本語でお話しいただけたのは良かったと思います。今後は、それぞれの教区で、シノドス最終文書の学びを深め、多くの人に霊における会話を体験していただき、その上で、ともに歩みなが聖霊の導きを識別する共同体に育っていきたいと思います。これからもシノドス特別チームでは必要に応じて講師を派遣しますし、様々な資料の提供を続けていきます。今後の各教区での取り組みに期待しています。
以下、6日午後6時配信、週刊大司教第223回、年間第23主日のメッセージです。
年間第23主日
週刊大司教第223回
2025年9月7日前晩
9月最初の主日は、「被造物を大切にする世界祈願日」であります。
世界のキリスト教諸教派は、ともに、9月1日からアシジの聖フランシスコの祝日である10月4日までを「被造物の季節」と定め、この地球、すなわちわたしたちがともに暮らす家のために祈り、またそれを守る行動をとるように呼びかけています。カトリック教会もこのエキュメニカルな活動に参加しており、日本の教会はこの期間を「すべてのいのちを守るための月間」として様々な取り組みが行われています。また今年は、教皇フランシスコの回勅「ラウダート・シ」が発表されてから10年となる節目の年でもあり、環境保全活動にとどまらずそれを土台とした信仰的な回心の必要性を、教会はさらに強調しています。
教皇レオ十四世もこの世界祈願日にあたってのメッセージを発表されており、今年のテーマを、教皇フランシスコがすでに選ばれていた、「平和と希望の種」とされています。
メッセージの中で教皇は、「イエスは、説いて教える際、しばしば種のたとえを用いて神のみ国について語られました」の述べ、時間がかかる試みかもしれないが、わたしたちは神がのぞまれた世界のあり方を、すなわち「平和と希望」を実現するために、大地にまかれた種のように、忍耐を持って、具体的な取り組みと呼びかけを続けるようにと励まされています。
その上で教皇は、「自然破壊による打撃は、すべての人に同じように作用しているわけではないという認識は、いまだ十分に共有されていないようです。正義と平和を踏みにじることは、いちばん貧しい人、もっとも隅に追いやられた人、排除された人が、もっともしわ寄せを被るのです。この点で、先住民族のコミュニティの苦しみは象徴的です」と指摘され、その存在すら忘れ去られた人たちに心を向けるようにと呼びかけます。
ルカ福音は、弟子となる条件として、「自分の十字架を背負ってついてくる者」であれと述べたイエスの言葉を記します。同時に、「父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、更に自分の命であろうとも、これを憎む」ことを不可欠であると述べ、この世の常識を遙かに超える行為を、愛に基づいて選択することが不可欠であることを名確認します。
パウロは第一コリントの1章17節で十字架の意味を、神ご自身によるすべてを賭した愛のあかしの目に見える行いそのものであると記します。この世の知恵に頼って愛をあかしするのではなく、すべてをうち捨て全身全霊を賭して神の愛をあかししたイエス。それこそが十字架の持つ意味であることをパウロは強調します。
ですから、イエスが求める十字架は、単に苦労をしろと命じているのではありません。人間の知恵が作り上げた常識の枠にとらわれず、自らの全身全霊を賭して、神の愛をあかしするための行動をせよと求めておられます。
神の愛を証しするために、わたしたちがいま捨てなくてはならない常識の枠は何でしょうか。そしていま歩むべき十字架の道は、どの道でしょうか。聖霊の導きのうちに識別したいと思います。