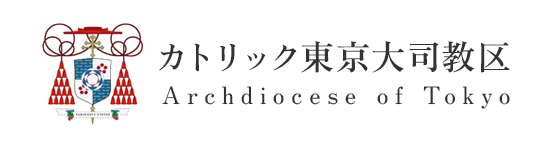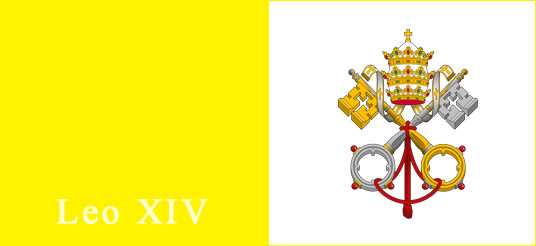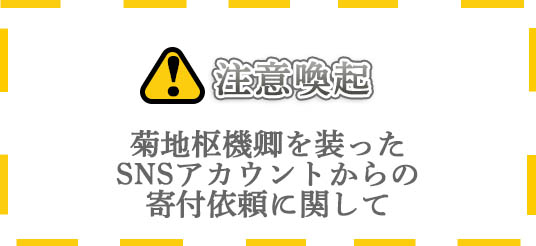大司教

週刊大司教第二百二十一回:年間第二十一主日
2025年08月25日

8月も後半に入り、年間第21主日となりました。暑い毎日が続いています。体調はいかがですか。東京では、朝晩やっと涼しさを感じるようになりましたが、それでも日中は熱帯のようです。
わたしは昔、若い頃に、アフリカのガーナで働いていましたが、日本の気候も熱帯のようになったと感じます。ガーナは赤道の少し北ですから、今の時期は夏、つまり雨期であります。雨期といっても朝から晩まで雨が降っているのではなく、いわゆるスコールというのか、一日の後半に、やにわに雲が湧き出してバケツをひっくり返したような雨が一時間くらい降り注いで、あとは晴れているような毎日でした。その雨が降っている間に、台風のような風が吹き荒れて、この時期には屋根を飛ばされる家も相次ぎました。なにか日本の夏も、そのような気候に変化しているように感じます。しかし、気温的には、ガーナの雨期の方が、遙かに涼しく感じます。
教皇様は世界の平和を祈るために、先日、天の元后聖母マリアの祝日である8月22日(金)に、平和のために断食と祈りを捧げるように呼びかけられました。「聖地、ウクライナ、また世界の他の多くの地域で、戦争によって傷つけられ続けて」いる現実を取り上げ、祈りを求められました。わたしたち日本の教会は、ちょうど平和旬間を終わったところですが、この日曜日、24日の主日には、是非とも世界の平和のためにともに祈りを捧げてくださるようにお願いします。
以下、23日午後6時配信、週刊大司教第221回、年間第21主日のメッセージです。
年間第21主日
週刊大司教第221回
2025年8月24日前晩
救いはどのようにして得られるのか。この問いかけは、時代や文化、また宗教の違いを超えて、人類に共通の課題の一つであります。
いのちの創造主であり、わたしたちに賜物としてこのいのちを与えてくださった神は、すべての人が救われることを望まれているのは確実です。ご自分が賜物として与えられたすべてのいのちを愛おしく思われる神は、その救いがすべての人におよぶことを望まれています。
「キリストの苦しみと死は、いかにキリストの人性が、すべての人の救いを望まれる神の愛の自由で完全な道具であるかを示して」いると、カテキズムの要約に記されています(119)。ですからキリストが語り行ったこと、すなわちイエス・キリストの福音が一人でも多くの人に伝わることは、神の望まれる救いの計画の実現のために不可欠であります。その意味でも、わたしたちの第一の使命は、福音をありとあらゆる手段を通じて、一人でも多くの人に告げ知らせることであります。救いはわたしだけのものではありません。
その救いの計画の中でわたしたちがなにもしないで、ただひたすらに自分の救いだけを待ち望んで、自分勝手に生きていたのであれば、果たしてそこに救いはあるのだろうかと、今日のルカ福音は問いかけています。
イエスは、「救われる者は少ないのでしょうか」という問いに、直接には答えていません。なぜならば、救われるはずの者は、すべての人だからです。しかしせっかくのその「すべて」を、「少ない」者としてしまうのは、人間の怠惰と努力のなさであることをイエスは指摘します。「狭い戸口から入るように努めなさい」というイエスの言葉は、ともすれば苦難の道を避けて安楽な道を選んだり、準備を怠り無為無策に過ごしているわたしたちこそが、神からの救いへの招きに応えようとしていないのだという事実を指摘しています。
現代社会の象徴でもあるインターネット上でのインフルエンサーと呼ばれる人たちをローマに招いて、7月末に行われた聖年の行事で、教皇レオ十四世は、デジタルコミュニケーションを通じて福音宣教することの重要性を説きながら、こう言われました。
「教会は、歴史を通じて文化的な挑戦を受けても、決して受け身な姿勢にとどまることはありませんでした。教会は、善と悪を識別することによって、すなわち、変化し、変容し、清めることを必要とするものから善を識別することによって、すべての時代をキリストの光と希望によって照らそうとつねに努めてきました」
その上で教皇レオ十四世は、「単にコンテンツを生成することではなく、心の出会いを生み出すことです。そのために、苦しむ人、主を知ることを必要とする人を探し求めなければなりません。彼らが傷をいやし、自分の足で立ち上がり、人生に意味を見いだせるようになるためです。何よりもまず、このプロセスは、自分の貧しさを受け入れ、あらゆる偽りを捨て、自分自身が福音を本質的に必要としていることを認識することから始めなければなりません」と指摘されました。自分の利益や名誉のためではなく、他者の必要に目を向け、常に救いの福音をもたらすために行動することの重要性を強調されました。
わたしたちも、狭い門を避けるものではなく、困難への挑戦から目を背けず、隣人の必要に常に心の目を見開き、積極的に行動するものでありましょう。