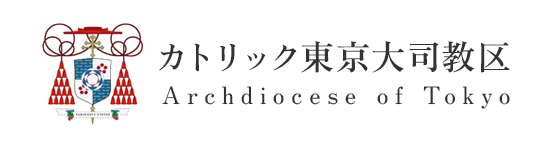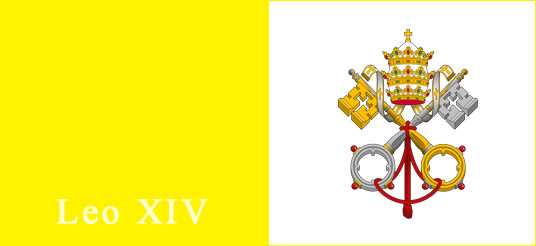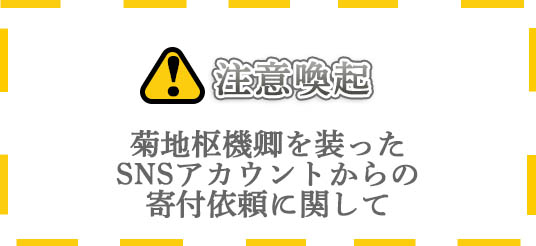大司教

週刊大司教第二百十六回:年間第十五主日
2025年07月14日

暑い毎日が続いています。7月13日の主日は年間第15主日です。(写真は、教皇様が夏休みのため滞在されるカステル・ガンドルフォ遠景)
わたしは、7月13日は岩手県宮古市のカトリック宮古教会で、主日のミサを捧げました。宮古市はわたしの生まれ故郷であり、そのときに洗礼を受けたのがカトリック宮古教会で、当時宮古を始め岩手県を担当していたスイス人の宣教師(ベトレヘム外国宣教会)が、チューリヒあたりのドイツ語を話すスイス人であった関係で、当時まだドイツ人宣教師が多くいた神言修道会に入ることになりました。その意味で、いまのわたしの信仰生活の基礎は宮古にありますので、特にこのたび枢機卿にしていただいてまだ宮古を訪問していませんでしたので、宮古教会のみなさまへの感謝を込めてミサを捧げさせていただきました。
以下、12日午後6時配信、週刊大司教第216回、年間第15主日のメッセージ原稿です。
年間第15主日
週刊大司教第216回
2025年7月13日前晩
ルカ福音書は、よく知られた「善きサマリア人」の話を伝えています。
教皇レオ十四世は、5月28日の一般謁見でこのたとえ話を取り上げ、こう述べておられます。
「人生は出会いによって作られます。そして、この出会いの中で、わたしたちの真の姿が現れます。わたしたちは他者の前に立ち、他者のもろさや弱さを目にします。そして、なすべきことを決断することができます。すなわち、その人の世話をするか、何事もなかったかのようなふりをするかです。」
その上で教皇様は、「あわれみは具体的な行動によって示されます。・・・サマリア人は、近づきます。なぜなら、誰かを助けたいと思うなら、距離を保とうとは考えません。あなたは関わり、汚れ、もしかすると汚れまみれにならなければならないかもしれません。サマリア人は傷口を油とぶどう酒できれいにしてから包帯をしました。その人を自分のろばに乗せました。すなわち、重荷を負いました。なぜなら、真に人を助けたいなら、人の苦しみの重みを進んで感じなければならないからです。サマリア人はその人を宿に連れて行き、・・・必要ならさらに支払うことを約束しました。なぜなら、他者は、配達すべき荷物ではなく、ケアすべき人だからです」と述べ、「イエスが立ち止まってわたしたちの世話をしてくださったすべての時を思い起こすなら、わたしたちはいっそうあわれみ深くなることができる」と呼びかけています。
律法の専門家のイエスに対する問いかけは、例えば労働の対価としてそれに見合った報酬があるべきだというような意味合いです。しかし、神と私との関係の中では、これだけすればこれだけ報いがあるはずだ、という論理は通用しません。なぜならば、神を信じるとは、神からの一方的な働きかけに身を任せることに他ならないからです。
言ってみれば見事な回答をした律法の専門家に対して、イエスは、「よく知っているではないか。それではその神の望みを具体的に生きなさい」と告げます。しかし律法の専門家は、自分の常識にこだわり、隣人の範囲を明確に定めようとします。
善きサマリア人の話は、神が求められているいつくしみのおもいに心を動かされることなく、自分の殻の中で生きようと目を閉じる二人と、神のいつくしみの心に動かされて、目を見開き困窮する隣人の存在を認め、いつくしみに具体的に生きようとしたサマリア人の対比を描きます。
わたしたちが求められているあわれみ深い行動は、単にわたしたち自身の優しい性格によっているのではなくて、それは神ご自身の思い、張り裂けんばかりに揺さぶられている神のあわれみの心に、わたしたちが自分の心をあわせることによって促される行動です。
神ご自身は、ただ傍観者としてあわれみの心を持ってみているのではなく、自ら行動されました。自ら人となり、十字架での受難と死を通じて、ご自分のいつくしみを目に見える形で生きられました。
わたしたち一人ひとりの生活での出会いを通じて、また教会の組織を通じて、神のいつくしみの心のおもいを身に受けて、具体化して参りましょう。