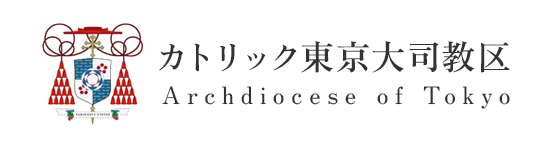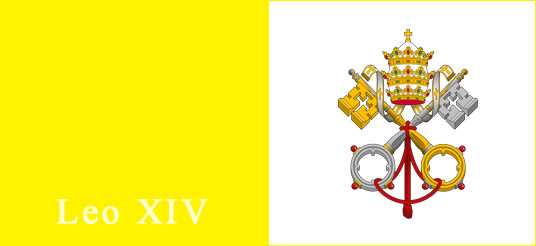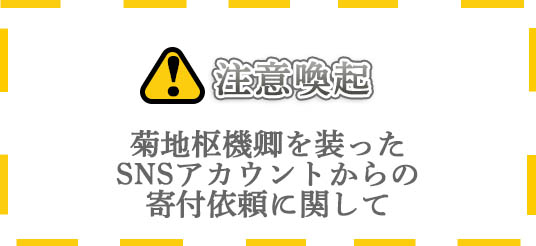大司教

週刊大司教第二百四回:四旬節第五主日
2025年04月07日
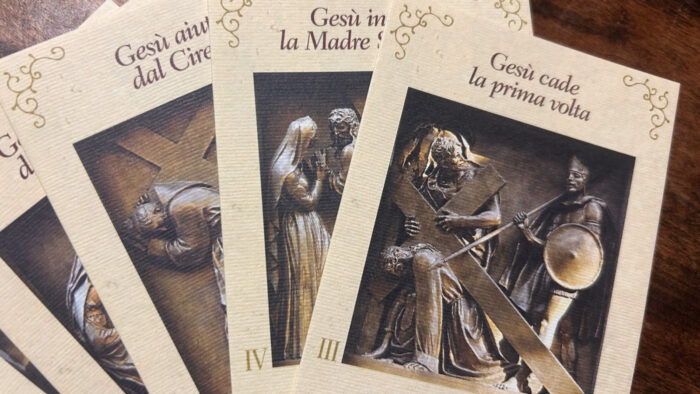
四旬節も終わりに近づき、もう第五主日です
3月23日深夜に出発して、29日お昼頃帰着で、ローマに出かけておりました。もともとは一年に一度、この時期に教皇様にお会いして、国際カリタスの活動報告をすることにしていたのですが、もちろん現在の教皇様の健康状態もあり謁見はキャンセルになりましたが、それ以外にも国務省を始め総合的人間開発省、東方教会省、諸宗教対話省、キリスト者一致推進省、広報省、教皇庁未成年者保護委員会、シノドス事務局を、国際カリタスの事務局長と二人で訪問して回りました。

またその間に、枢機卿としての名義教会であるサン・ジョバンニ・レオナルディ教会のアントニ・サミィ・エルソン主任司祭(向かって右端)始め助任司祭と小教区財務委員の信徒の方の訪問を受け、さらに主任司祭と一緒に教皇庁儀典室のモンセニョールを訪問し、10月9日夕方6時に予定されている着座式の打ち合わせも行いました。ローマのどちらかというと郊外の住宅地にある小教区であり、長年、枢機卿の名義教会になることを申請していてやっと夢が叶った。住宅街の共同体なので、日曜のミサの参加者は大勢であり、様々な活動のある教会だ。当日は日本からの訪問者も大勢いるだろうし、当小教区出身の司祭や司教も来るので、聖堂に入りきらない場合は、隣の学校のグランドで野外ミサをするとのことです。いまから楽しみです。イタリア語ですが、小教区のホームページです。なお司牧を担当しているのは16世紀に聖ジョバンニ・レオナルディが創立したOMD(Ordo Clericorum Regularium Matris Dei)と言う修道会司祭ですが、この会の正式名称をどのように邦訳するのか思案中です。
その間に、イタリア国政放送RAIのテレビのインタビューがあり、さらには国際カリタスの夏の聖年の青年行事の打ち合わせや、国際カリタス法務委員会との顔合わせなど、盛りだくさんでした。

バチカン周辺は思ったほどの人出ではなかったものの、聖年の巡礼団が多く集まり、サンタンジェロ城付近からコンチリアツィオーネ通りにサンピエトロ大聖堂までまっすぐに700メートル近い特別通路が設けられてあり、途中信号などがあるのでボランティアの時間調整や誘導にしたがって、祈りとともに歩んでいました。サンタンジェロ城の近くに登録ブースがあり、ここで先頭を行く十字架を貸してもらえるようです。

ローマ市内は未だにそこら中で道路工事をしていましたが、昨年末に枢機卿親任式で訪れた際には絶対終わるのは不可能と思ったバチカン周辺の工事は、なんと見事に終わり、閉鎖されていた地下トンネルなども再開して、渋滞も少なくなっていました。ただ、今回も国際カリタス事務局のすぐ近くの小さなホテルに泊まったのですが、お値段が昨年とは比べものにならないくらい高騰していました。

教皇様は宿舎であるサンタマルタの家に戻られていますが、パロリン国務長官によれば、二ヶ月本当に休んでくれれば、なんとか復帰できるだろう。教皇様がしっかりと休むようにすることが、我々の務めだと言われ、回復の度合いにもよりますが、いままでのようなペースでの仕事は難しくなるのでスタイルを変更しなくてはならないとのことでした。どうか続けて、教皇様のためにお祈りください。
以下、5日午後6時配信、週刊大司教第204回、四旬節第5主日のメッセージ原稿です。
※印刷用はこちら
※ふりがなつきはこちら
四旬節第五主日
週刊大司教第204回
2025年4月6日前晩
ヨハネ福音は、「姦通の現場で捉えられた女」の話を伝えています。「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」と言うイエスの言葉がよく知られています。もちろんこの場において、本当に罪を犯したことのないものは、神の子であるイエスご自身しかおられません。さすがに神に挑戦するような思い上がった人は、当時の宗教的現実の中で、そこにはいなかったと福音は伝えています。
しかし同じことが、今の時代に起こったとしたらどうでしょう。とりわけ、バーチャルな世界でのコミュニケーションが匿名性の影に隠れて普及している今、同じことが起きたのであれば、あたかも自分こそが正義の保持者であるというような論調で、この女性を糾弾する声が多く湧き上がるのではないでしょうか。何という不遜な時代にわたしたちは生きているのでしょう。時にその不遜さは、自分が虐げている弱い相手に対して、自分に対する感謝が足りないなどと、さらにとんでもない要求すらして相手を糾弾します。
この福音の物語は、時代と文化の制約があるとはいえ、共犯者であるはずの男性は罪を追及されることがなく、女性だけが人々の前に連れ出され断罪されようとしています。同じ罪を形作っているにもかかわらず、女性だけが批判される構図は現代でも変わりません。それどころか、ハラスメントなどの暴行や虐待の事案にあって、あたかも被害者に非があるかのような批判の声が聞かれることすらあります。
神の愛といつくしみそのものであるイエスは、犯された罪を水に流して忘れてしまうのではなく、ひとり責めを受けいのちの尊厳を蹂躙されようとしている人を目の前にして、その人間の尊厳を取り戻すことを最優先にされました。もちろん共同体としての秩序と安全を守ることは大切ですし、社会においてもまた宗教共同体においても、掟が存在しています。
イエスの言葉は、掟を守ることに価値がないとは言いません。イエスの言葉は、掟が前提とするひとり一人の人間の尊厳に言及しています。なぜならばその尊厳ある一人一人が共同体を作り上げているのであって、共同体が人を作り上げているからではありません。イエスは、そのような場に引き出され、辱められ、人間の尊厳を蹂躙されている女性の、そこに至るまでの状況を把握することもなく、掟を盾にして尊い賜物であるいのちの尊厳をないがしろにしている現実のただ中で、一人のいのちの尊厳を守ろうとしています。その存在を守ろうとしています。わたしたちの時代は、誰を、そして何を最優先にしているのでしょうか。
今年の四旬節メッセージ「希望をもってともに歩んでいきましょう」で教皇様は、回心について三つの側面から語っておられます。その三つ目のポイントは、約束に対する「希望をもって」ともに歩むことですが、教皇様はそこにこう記しています。
「回心への第三の呼びかけは、希望への、神とその大いなる約束である永遠のいのちを信頼することへの招きです。自らに問いましょう。主はわたしの罪をゆるしてくださると確信しているだろうか。それとも、自分を救えるかのように振る舞っているのではないだろうか。救いを切望し、それを求めて神の助けを祈っているだろうか。歴史の出来事を解釈できるようにし、正義と兄弟愛、共通の家のケアに務めさせ、だれ一人取り残されることがないようにする希望を、具体的に抱いているだろうか」
わたしたちは、神からのゆるしをいただいて生かされていると心に刻むとき、神の前で謙遜に生きることを学びます。神の前に謙遜になるとき、はじめて、同じ神の愛によっていのちを与えられ生かされている兄弟姉妹と、ともに歩むことの大切さを理解することが可能になります。ひとり一人の人間の尊厳を尊重し、虐げられている人の尊厳を回復しようとする主のいつくしみに倣いましょう。