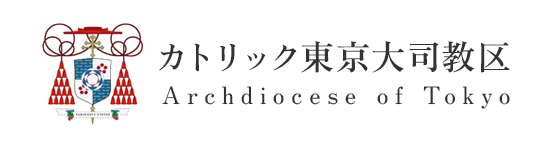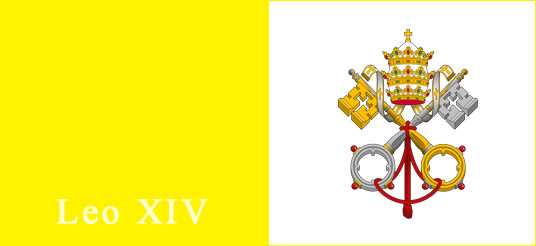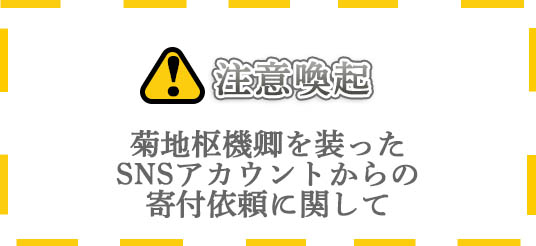大司教

週刊大司教第二百三回:四旬節第四主日
2025年04月01日

ミャンマーのマンダレー付近を震源に、大きな地震が発生しました。隣国のタイでも被害が出ていますが、現在の政治状況から、情報がバンコクからの映像が多くあり、なかなかミャンマーからの情報が伝わってきません。断片的な情報でも、建物の倒壊など大きな被害が出ているようです。
3月29日午後3時頃のNHKのサイトによれば、「ミャンマーの国営テレビは29日、SNSに投稿し、今回のミャンマー中部で発生した大地震で全国でこれまでに1002人が死亡し、2376人がけがをしたと伝えました」とのことですので、まだまだ地方からの情報が集約されていないことでしょうから、被害はこれからさらに拡大するであろうと推測します。
ミャンマーはコロナ禍の真っ最中、2021年2月1日のクーデター以降不安定な国内状況が続いており、少数民族の多い周辺部では、戦闘が続いています。東京教区はミャンマーの教会をケルン教区と共に長年にわたって支援しており、ミャンマーの教会は姉妹教会です。
特にこの数年は、マンダレー教区で神学校の建設などを支援してきましたが、そのマンダレーが震源地に近いと言われていますので、大変心配しております。この数年の政情不安の中で、平和と民族の融和を訴えるカトリック教会への攻撃が続き、いくつかの教区では、カテドラルが爆撃されたりして、司教様自身が難民となっているところもあります。そこにこの大地震です。
今回の地震に遭遇された多くの方々、特にミャンマーとタイの皆さんのために、祈りたいと思います。
なお募金の問い合わせをいただいていますが、状況が明確になるのをしばらく待ち、カリタスジャパンの判断も待ちながら、週明けには、教区としての対応をお知らせすることに致します。
以下、3月29日午後6時配信、週間大司教第203回目のメッセージ原稿です。
※印刷用はこちら
※ふりがなつきはこちら
四旬節第四主日
週刊大司教第203回
2025年3月30日前晩
ルカ福音は、よく知られている「放蕩息子」のたとえ話を記しています。この物語には、兄弟とその父親という三名が、主な登場人物として描かれています。
当時の社会状況とその背景にある宗教的な掟に基づいて、罪人とされている人々に寄り添おうとされたイエスに対して、その掟を厳しく追及する人々は不平を漏らします。
「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている」
この不平の言葉は、今を生きるわたし達の間でも聞かれる言葉であります。こう語る人の視点は、実は「罪人」にあるのではなく、自分自身に向けられています。すなわち、「本来大切にされ受け入れられるべきなのは、正しいわたしであるはずだ」という心持ちであります。正義は自分にあるはずなのですから、それを否定し、正義を持たない人たちを優遇するイエスを、理解することができません。
東京ドームのミサの説教で、教皇フランシスコは、「傷をいやし、和解とゆるしの道をつねに差し出す準備のある、野戦病院となること(東京ドームミサ説教)」を教会共同体に求められました。神のいつくしみの深さに包まれ、その行動の原理に倣うことをわたしたちに説いておられます。
弟を迎え入れた父親は、「いなくなっていたのに見つかったからだ」という言葉の前に、「死んでいたのに生き返り」と付け加えています。父親の価値基準は正しさにあるのではなく、家族という共同体に繋がって生かされているのかどうかにあります。ですから弟を迎え入れた父親に対して不平を言う兄に、「お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ」と告げるのです。
共同体の絆から離れていることは、いのちを生きていたとしても「死んでいる」ことであって、その絆に立ち返ったからこそ弟は「死んでいたのに生き返り」と父親が語っているのです。共同体の絆、すなわち連帯の絆に結ばれて、人はいのちを十全に生きることができるのです。父親の優しさとは、罪に対して目をつむることではなく、共同体の連帯の絆に立ち返らせようとする愛の心であって、神の正義はそこにあります。
今年の四旬節教皇メッセージ、「希望をもってともに歩んでいきましょう」いおいて回心について三つの側面から語る教皇は、二つ目の側面である「ともに歩む」ことについてこう記しています。
「ともに歩む、シノドス的であること、これが教会の使命です。キリスト者は決して孤高の旅人ではなく、ともに旅するよう呼ばれています。聖霊は、自分自身から出て神と兄弟姉妹に向かうよう、決して自分自身を閉じないよう、突き動かしておられます」
その上で教皇は、ともに歩むことで共同体の絆を回復させることの大切さを説きこう記します。
「ともに歩むということは、神の子としてともに有する尊厳を基盤とした一致の作り手となるということを意味します。それは、人を踏みつけたり押しのけたりせず、ねたんだりうわべの振る舞いをしたりせず、だれも置き去りにしたり疎外感を覚えさせたりせずに、肩を並べて歩むということです」
自らの正義を振りかざし、他者を糾弾し排除しようとする誘惑は、現代社会に満ちあふれています。わたし達は、放蕩息子を迎え入れた父親のように、共同体の絆にいのちを回復させ、ともに歩もうとする姿勢が、求められています。