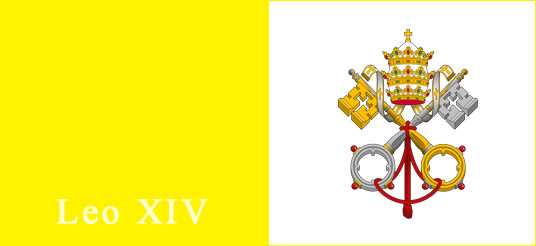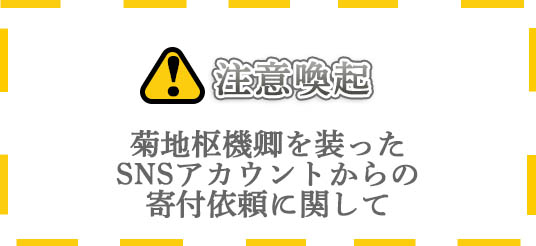大司教

週刊大司教第三十回:年間第十一主日
2021年06月14日
6月は「みこころの月」と言われます。「みこころ」は、主イエスの心のことで、以前は「聖心」と書いて「みこころ」と読んでいましたが、近頃は「み心」と記されることが多いように思います。イエスのみこころは、わたしたちへのあふれんばかりの神の愛そのものです。十字架上で刺し貫かれたイエスの脇腹からは、血と水が流れ出たと記されています。血は、イエスのみこころからあふれでて、人類の罪をあがなう血です。また水が、いのちの泉であり新しい命を与える聖霊でもあります。キリストの聖体の主日後の金曜日に、毎年「イエスのみこころ」の祭日が設けられ、今年は6月11日でありました。
みこころの信心は、初金曜日の信心につながっています。それは17世紀後半の聖女マルガリータ・マリア・アラコクの出来事にもとづく伝統であります。聖体の前で祈る聖女に対して主イエスが出現され、自らの心臓を指し示して、その満ちあふれる愛をないがしろにする人々への悲しみを表明され、人々への回心を呼びかけた出来事があり、主はご自分の心に倣うようにと呼びかけられました。そしてみこころの信心を行うものには恵みが与えられると告げ、その一つが、9ヶ月の間、初金に聖体拝領を受ける人には特別なめぐみがあるとされています。イエスは聖女に、「罪の償いのために、9か月間続けて、毎月の最初の金曜日に、ミサにあずかり聖体拝領をすれば、罪の中に死ぬことはなく、イエスの聖心に受け入れられるであろう」と告げたと言われます。
1856年に教皇ピオ9世が「イエスのみこころ」の祭日を定め、さらにその100年後、教皇ピオ12世は、みこころの信心を深めるようにと、回勅をもって励ましを与えられました。さらにそれから50年後、教皇ベネディクト16世は、2006年5月15日付でイエズス会の総長に宛てて書簡を送り、イエスのみこころへの信心は決して過去のものではなく現代的な意味があると述べながら、次のように記します。
「内面的に神を受け入れた人は皆、神によって形づくられます。神の愛を経験した人は、その愛を「召命」として生きなければなりません。人はこの「召命」にこたえなければなりません。主は「わたしたちの患いを負い、わたしたちの病を担った」(マタイ8・17)かたです。この主に目を注ぐことによって、わたしたちは人の苦しみと必要にもっと気づくことができるようになります。
槍で刺し貫かれたイエスの脇腹を礼拝しながら観想することにより、わたしたちは、人びとを救おうとする神のみ旨を感じることができるようになります。この観想によって、わたしたちは、救いをもたらす神の憐れみに自分をゆだねることができるようになります。それと同時に、この観想は、神の救いのわざにあずかり、神の道具となりたいというわたしたちの望みを強めます。」(全文は中央協議会のHPで)
みこころの月にあたり、イエスを通じて具体的に表された神の愛の心に触れ、それを自らの心とし、倣って生きることが出来るように、努めたいと思います。
以下、12日午後6時配信の「週刊大司教」第30回目のメッセージ原稿です。
※印刷用はこちら
※ふりがなつきはこちら
年間第11主日
週刊大司教第30回
2021年6月13日前晩
「神の国を何にたとえようか。・・・それは、からし種のようなものである」と語るイエスの言葉を、マルコ福音は伝えています。
取るに足らない小さな種から始まって、「葉の陰に空の鳥が巣を作れるほどの大きな枝を張る」までに育っていく過程を述べて、神の創造の業が人間の常識をはるかに超えた神秘のうちにあることを思い起こさせながら、イエスは神の国の実現への道を語ります。
エゼキエル書も同じように、レバノン杉の小さな梢を切り取り、山の上に移すことで、今度は大きな枝を張るレバノン杉が育っていくことを記し、それをつかさどる神の力の偉大さを伝えます。
パウロは、わたしたちの永遠の住みかは天にあるのだとしても、この地上での生活には重要な意味があることを指摘し、「体を住みかとしていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい」と記します。
すなわち、わたしたちは、主とともに天上の神の国で永遠の喜びのうちに生きることを望んでいるとしても、同時に、今生きているこの世界の現実の中で、同じように神に喜ばれるものとして、主から与えられた使命に忠実に生きる務めがあることが、パウロの言葉から示唆されています。
わたしたちには、主イエスの福音を、ひとりでも多くの人に伝えるという使命が与えられています。その業は、派手なパフォーマンスによって達成されるのではなく、小さな努力の積み重ねの上に成り立つのだということを、からし種のたとえから学びたいと思います。一人ひとりの小さな働きは、まさしくわたしたちが播く小さなからし種であります。しかしその種は、神によって育まれる限り、人間の常識をはるかに超える実りをもたらします。救いの業は、神の業であって、わたしたち人間の業ではありません。
去る5月11日、教皇フランシスコは、自発教令「アンティクウム・ミニステリウム」を発表され、信徒の奉仕職としての「カテキスタ」を正式に制定されました。
カテキスタというこの奉仕職は、決して新しいものではなく、すでに新約聖書の中に、初代教会における務めとしてその役割を見いだすことが出来ます。教会は当初から、聖霊の働きに従順に従い、教会の働きのために生涯をささげた信徒によって果たされる、さまざまな奉仕職によって支えられてきました。
第二バチカン公会議以降、教会は福音化の働きにおける信徒の役割の重要性を強調してきました。第二バチカン公会議の教会憲章に、こう記されています。
「信徒に固有の召命は、現世的なことがらに従事し、それらを神に従って秩序づけながら神の国を探し求めることである。自分自身の務めを果たしながら、福音の精神に導かれて、世の聖化のために、あたかもパン種のように内部から働きかけるためである」(31)
カテキスタは、入信の秘跡の準備から、信徒の生涯養成にいたるまで、神の民に奉仕するための信徒の召命であり、社会におけるパン種として働きかける生き方でもあります。パン種のように、またからし種のように、小さな一人ひとりの忠実な奉仕が、聖霊の導きのうちに、神の国の実現のために大きな実りを生み出します。わたしたちは小さな事に忠実に生きるよう、呼ばれています。
新しく制定された信徒の奉仕職としてのカテキスタに限らず、キリスト者には、すべからく自分の召命に生きる務めがあります。神からの呼びかけに忠実なものでありましょう。