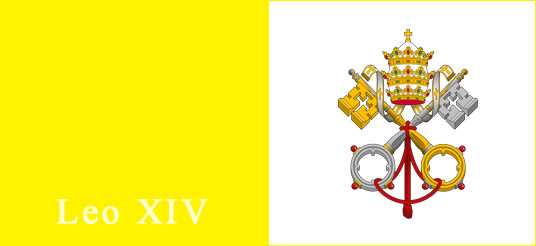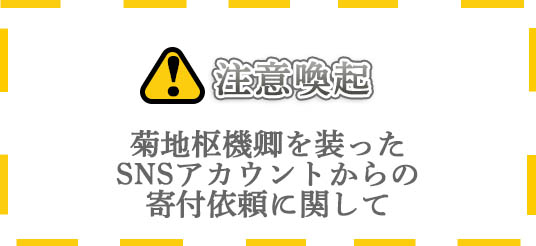大司教

あれから27年
2022年01月17日
今からちょうど27年前、1995年1月17日に、阪神淡路の大震災が発生しました。淡路島北部を震源とした最大震度7の地震は、6434人の方々のいのちを奪い、その後も様々な困難を地域に残しました。(写真は、大震災後の火災の後に残った、鷹取教会のイエス像。撮影は2009年11月)
27年が経過した今日、あらためて亡くなられた方々の永遠の安息を祈ります。また昨日から本日早朝、震災発生時刻の午前5時46分に合わせて、多くの方が祈りを捧げました。その後の東北の大震災や現在のコロナ禍と、心の平安が乱される出来事が続き、いわば暗闇の中をさまよい続けているような思いを抱いてしまいます。共に祈りを捧げ、闇に輝く真の光を求めながら、心の平安を願いたいと思います。
以下、ちょうど10年前、阪神淡路の大震災から17年目に記した「司教の日記(2012年1月17日)」から、再掲します(リンク抜けなど、一部書き直してあります)。
1月17日です。阪神淡路大震災から17年。亡くなられた多くの方々のために祈ります。同時にあの日から全く新たな時間を刻み始めた多くの方々の心の平安を祈ると共に、これからの歩みにも祝福と守りを祈ります。
昨日の梅田でのフォーラム(2012年1月16日に大阪梅田教会で開催された第7回修道会宣教会フォーラム)でも「あの日からもう17年」という言葉が何度も聞かれました。大震災以降の復興に関わった多くの方々、そして復興を力強く歩んでこられた多くの方々にとって、昨年の東北の大震災は17年前の心持ちをあらためて思い起こす「とき」になったのではと思います。歴史の流れの中で、ある「ひととき」にいったい自分がどこで何をしていたかなんて、そう簡単に覚えているものではありません。しかし衝撃的な出来事があったときを、私たちは簡単に忘れません。それは私たちにとって、1995年1月17日であり、2011年3月11日ではないでしょうか。その日の自分を思い出すとき、そのとき、その瞬間に感じた思いをしっかりと思い起こしたいと思いますし、そのあとに自分が何を考え何をしたのかをも、さらにはどうしてそうしたのか、そうしなかったのかをも、しっかりと思い出してみたいと思います。結局はそれが今を生きる自分を支える柱、自分の人生の価値観を反映しているからです。
17年前は私にとって、今に至るまでのカリタスジャパンとのつきあいが始まった年でした。とはいえ、それは阪神淡路大震災ではなかったのです。1月17日の朝、私はマニラのホテルのベッドの中でNHKのニュースを見ていました。信じられない光景と、国内にいないということだけで感じるもどかしさで、ただただ落ち着かない時間を過ごしていたことを覚えています。その数週間後、日本に戻った私に舞い込んできたのは神戸に行くことではなく、カリタスジャパンからの依頼でザイール(現コンゴ民主共和国)に出かける話でした。その一年前に起きた虐殺事件後混乱が続くルワンダから大量の難民が出ている。その難民キャンプがあるザイールに行ってほしい。すでにその数ヶ月前から継続していたカリタスジャパンによる難民救援事業の、最後の派遣組に参加することになりました。すでに派遣されていた塩田師と二人のシスターに助けられて、3ヶ月弱の派遣をこなすことができました(4名のうち私だけフランス語が話せませんでした)。それ以来、今に至るまで、様々な役割でカリタスジャパンに関わっています。
さて、そうやって思い出してみると、当時もカリタスジャパンの要請にこたえて、全国の女子修道会がシスターを現地に派遣してくださったのでした。つまり、今東北で行われている「シスターズ・リレー」の原型は、17年前のルワンダ難民救援にあったのでした。東北の大震災のあとに、仙台教区サポートセンターとの連携の中でシスター達がボランティアーベースに継続して派遣されてきています。どこの修道会だとかそういった違いを超え(つまりは、昨日の話に出た「枠」を超えて)、異なる修道会の会員達が連携しながら順番に現地入りしてくるその機動力は、17年前のルワンダと同様、女子修道会の底力を感じさせるものがあります。現在のカトリック教会オールジャパンの被災地支援を、幅広く支えているのはシスター達の底力だと思います。そういった原動力があるからこそ、さらに教会内外の多くの人が引き寄せられて現場に駆けつけるのでしょう。
とはいえ、昨日のフォーラムでも少しそのことに触れたのですが、時間の経過と共に考えて行かなくてはならないこともあります。阪神淡路の復興支援の過程における地域共同体の再生について私自身がよく知っていないこともあるのですが、現在の東北における復興支援においても、17年前の体験をふり返って常に見直しが不可欠であろうと思います。主役は誰なのかをたびたび思い起こし、なんのために、どうして、なにをと自分たちに問いかけておくことは必要だと思っています。継続は力なりであると共に、どう継続させるのか、なぜ継続させるのかをも、常に考えておかなくてはと思うのです。
P.S. 「主役は誰か」は、私のいつものテーマです。決して善意ある自立した積極的ボランティア活動を否定するものではありませんが、そのときに心のどこかにとどめておいてくれればと思います。2005年に出版した「カリタスジャパンと世界」(サンパウロ刊)にちょっとそのあたりを書きました。その中から、次の一節を引用します。
『「アウトサイダーとしての自覚」
開発援助の世界ではしばしば「アウトサイダー」という言い方をしますが、どのような関わり方をするにしろ、第三世界の現実の中に存在することを義務づけられた者でない限り、アウトサイダー(よそ者)に「本当のこと」は分からないのです。ロバート・チェンバースという開発専門家は、「リアリティ」という言葉を使って、客観的に実在する現実を「物理的なリアリティ」、主観的な解釈による現実を「個人的なリアリティ」と呼びながら、開発援助の現場で問題になる後者の「個人的なリアリティ」に注目します。つまり、開発プロジェクトに限らず援助全般において、一体誰の「リアリティ」が主役となっているのかという問題です。援助が究極的には「困っている人を助ける」事を目的としているのであれば、当然その主役は「困っている人」のはずでしょう。であるならば援助活動において主役となるのは、「困っている人」の「個人的なリアリティ」でなければなりません。ところが実際には、援助する側の「リアリティ」が優先されてしまうことが多いのです。言い換えれば、援助する側の都合が優先されるということです。
なぜそうなってしまうのでしょう。それは援助する側に、「アウトサイダー」の自覚が足りないからなのです。あくまでも自分たちは「よそ者」であり、主役は現地の人たちであるという自覚が足りないからなのです。
「よそ者」には帰るところがあります。そこには安定した生活があります。病気になったら母国に帰れば済んでしまいます。多くの場合、「よそ者」は現地に居たとしても、明日の食べ物に困ることはありません。「援助する側」と「援助される側」の現実には、たとえ時間と空間を共有していたとしても、雲泥の差があるのです。特に短期間の訪問者には、決して現地の「リアリティ」が見えることはないでしょう。チェンバースは「周辺」と「中心」という概念を使って、第三世界諸国に長期に滞在する開発や援助の専門家も、結局は「リアリティ」が掴みきれないと指摘します。「周辺」つまり農村部の現実を、「中心」すなわち設備の整った都市部を起点として活動する専門家は、ある種のフィルターを通じてしか見ることが出来ないのだというのです。例えば、都市を起点とする専門家の農村部における活動が、移動の困難な雨期を避け乾期に集中するため、一年を通じての現地に生きる人たちの現実が見えては来ないこともあるのです。援助に携わる人間は、自分が常に「アウトサイダー」であり、結局は現地の人たちの「リアリティ」を掴み切れていないのだということ、また主役は「彼ら」なのだということを、常に自覚して行動しなければなりません』
追記 (2022年1月17日) この記事の掲載準備している間、トンガで海底火山の爆発があり、日本でも津波警報が発令されました。トンガの状況はまだ判然としませんが、被害を受けられた方々にお見舞いするとともに、安全をお祈りいたします。